【40代教員の退職カウントダウン58:退職まで残り3年6ヶ月】
はじめに
ここ数年、「クラスに外国籍の子が入った」という話を聞くことが珍しくなくなりました。実際、私のクラスにもイスラム文化を持つ児童が在籍しています。過去にはクラスの3分の1が外国籍という年もありました。
少子化で日本人児童生徒の数は減る一方、外国人労働者や留学生が増え、家族とともに来日する子どもも増えています。
この記事では、私が経験した学級経営の実例と工夫を中心に、外国籍児童生徒と学校現場の対応について整理します。
私は40代小学校教務主任(担任兼務)、2028年度末に正規教員を退職予定です。
詳しくはこの記事をどうぞ→【私が退職しようと決意した具体的経緯】
外国籍児童生徒が増える背景と現状
文部科学省の統計によると、公立学校に在籍する外国籍児童生徒は2012年の約7万人から2023年には約13万人へ倍増。特に愛知、神奈川、東京、大阪といった大都市圏で増加が顕著です。
私が2014年に担任したクラスでは、38名中14名が外国籍。中国・アメリカ・ペルー・ブラジル・シエラレオネなど多様な国籍の子どもたちでした。
- 3名は日本語が全く理解できず、母語課題の準備が必要。
- 他の子どもたちも、日本語の理解度に大きな幅がありました。
結果として、そのうち8名は週3時間の日本語取り出し授業を受け、10名にはふりがな付き教科書や特別なテストを準備しました。この状況は私の学級だけではなかったので、運動会はまさに「世界陸上」のような雰囲気でした(笑)

外国籍児童生徒が抱える課題
日本語の壁
- 会話はできても学習言語が不足し、教科書やテストでつまずく。
- 日本語ゼロの児童には母語課題や支援教材が必須。
文化や宗教習慣の違い
- 給食で食べられない食材や、宗教上の理由で行事に参加できないケース。
- 男女観や生活習慣の違いからトラブルが生じることもある。
保護者対応
- 日本語が通じにくく連絡が困難。特にウルドゥ語やパシュトゥ語などの日本であまり知られていない言語は通訳や辞書を見つけることも難しい
- 教育観や生活観の違いから誤解が起きることも。
例:アメリカ籍の保護者から「掃除を子どもにさせるのはなぜか」と質問を受け説明に苦労。

私の学級での実例
行事参加への配慮
- 修学旅行で神社参拝を避けたい児童には鳥居をくぐらないなど別ルートを提案。
- キャンプファイヤーで宗教的儀式(火の神の点火など)を避けたい児童には、点火後から合流してもらうなど柔軟に対応。
給食への配慮
- イスラム教児童には献立表を事前に確認し、豚由来のメニューは除外。弁当持参や代替食を準備してもらった。
- ラマダン期間中は「日中断食する友達がいる」とクラスに説明し、理解を促した。
- ネパールの1日2食の文化には、保護者に日本の3食文化を説明し、会食によるコミュニケーションの重要性を説明。
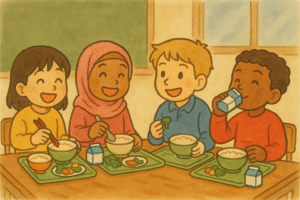
ジェンダー意識の指導
- イスラムの児童に女子の意見を軽視する態度が見られたため、「男女平等が学校の基本」というルールを繰り返し指導。
- 保護者対応でも「母親は男性教員を避けたい」「父親が女性教員を軽視する」などのケースがあり、男女平等は日本社会で必要な価値観として説明した。
保護者とのコミュニケーション
- アメリカ国籍の保護者の「なぜ子どもに清掃を強制するのか」という問い合わせに、清掃活動の意味や日本の文化を丁寧に説明。
- 通訳不足の言語(ウルドゥー語・パシュトゥー語など)では翻訳アプリを活用し、視覚的に伝える工夫もした。
私が取り組んだ工夫

① 総合学習で異文化理解
児童のルーツの国をテーマに調べ学習を行い、保護者をゲストティーチャーとして招きました。食文化や衣服を紹介してもらうことで、「日本の常識=世界の常識ではない」と学ぶ大切な時間になりました。
② 学級内ナショナルデー
外国籍児童が活躍できる場を作るため「学級内ナショナルデー」を設定しました。決められた曜日の挨拶や数字のカウントをポルトガル語や中国語で行い、日直が困ったら外国籍の児童にリードしてもらうようにしました。自信と誇りを持てる仕掛けでした。
※ポルトガル語の「起立 気をつけ お願いします」は「パラテ パラテデレッチョ ポルファボール」
③ 外国語活動に母国語を導入
英語活動の一部を他言語に置き換え、中国語やスペイン語を話す児童に“先生役”をしてもらいました。「英語ではこう言うけど、中国語では? スペイン語では?」と紹介してもらうことで、クラス全体が多言語に触れられました。
学校としてできること
- 日本語支援体制の整備:「日本語初期指導教室」などで数か月集中指導。
- 学校全体での共通理解:給食・行事対応を校内で統一し、担任一人に負担が集中しない体制を作る。
- ICTや翻訳の活用:翻訳アプリや生成AIを活用することで、保護者とのやりとりが格段に円滑に。
課題は多いですが、現場でできる工夫も少しずつ広がっています。「特別支援教育コーディネーター」の先生が各校に一人以上任命されているはずですので、その先生や管理職の先生に相談すると良いでしょう。
私がよく活用させてもらっていたのは東京都の日本語指導教材です。たくさんの言語がありますので一度見てみるといいかもしれません。
文化の違いを「摩擦」から「学び」に
外国籍の子どもがクラスにいると最初は戸惑うかもしれません。しかし、それは子どもたちにとって国際社会を生きる力を育む大きな機会です。
教師自身にとっても異文化理解を深めるチャンスであり、教育者としての幅を広げることにつながります。
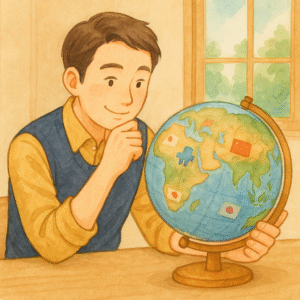
むすび
外国籍児童生徒は今後も増え続けます。課題は多いものの、工夫と柔軟な対応によって「文化の違いを学びに変える」ことが可能です。
子どもにとっても教師にとっても、異文化理解はかけがえのない財産になります。
合わせて読んでほしい シリーズ特別支援教育
「特別支援学級ってどんなところ?担任を経験した私がしんどさを解説」
「特別支援教育を理解したい!特別支援学級の担任におすすめの本3選」


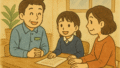
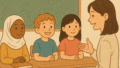
コメント