【40代教員の退職カウントダウン90:退職まで残り3年5ヶ月】
はじめに
2018年、学校教育に大きな転換点が訪れました。
長く「特別の時間」として扱われてきた道徳が、正式に「特別の教科 道徳」として教科化されたのです。
「子どもの心を育てる時間」が、成績をつける対象になった——。
現場では戸惑いの声もありましたが、そこには時代背景と明確な狙いがありました。
今回は、教員の教養シリーズとして現職教務主任の視点から道徳の教科化の意味と課題を整理してみます。
私は40代小学校教務主任(担任兼務)、2028年度末に正規教員を退職予定です。
詳しくはこの記事をどうぞ→【私が退職しようと決意した具体的経緯】
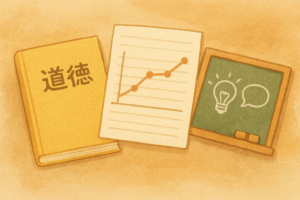
合わせて読みたい:教員の教養シリーズ
【若い先生のための日教組入門 ― 歴史と現在をざっくり知ろう】
【安倍政権の教育改革を振り返る──理念・成果・課題を中立的に整理する】
【教育基本法の改正って何だったの?──若手の先生にわかりやすく解説】
【教員免許更新制度はなぜ廃止されたのか?——制度が生まれた理由と、現場が感じた限界】
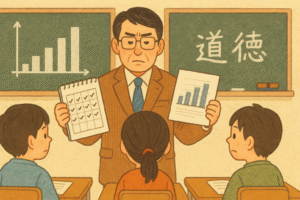
道徳の教科化とは何か
「道徳の教科化」とは、これまで「道徳の時間」として扱われてきた授業を、正式な教科の一つとして位置づけたことを指します。
そもそも道徳は、1958年に小学校に、同年中学校にも特設されました。当時の位置づけは「特別の教科」とされ、成績を付ける対象ではありませんでした。
その後、2015年の学習指導要領改訂により「道徳の教科化」が決定し、
- 小学校では2018年度から
- 中学校では2019年度から 本格的にスタートしました。
それまでの道徳は「学習指導要領に基づく教育活動の一環」であり、通知表で数値評価を行うことはありませんでした。
しかし教科化によって、道徳は「考え、議論する道徳」へと転換し、授業づくりや評価の在り方が大きく変化しました。
教科化が進められた背景
道徳が教科化された背景には、2000年代以降の社会状況の変化があります。
いじめ・不登校など教育への信頼低下
連日のように報じられるいじめ事件、不登校の増加、学級崩壊…。
こうした中で「道徳教育の再強化」が国レベルで求められるようになりました。
2006年には教育基本法が改正され、「公共の精神」「生命の尊重」など、価値教育の重要性が明記されています。

「考え、議論する道徳」への転換
戦後の道徳教育は、“価値を教え込む”印象が強く、形式的になりがちでした。
その反省から、新しい道徳は「一つの正解を押し付けない」方向に舵を切りました。
つまり、子ども自身が考え、他者と意見を交わし、価値観を深めていくことを重視しています。
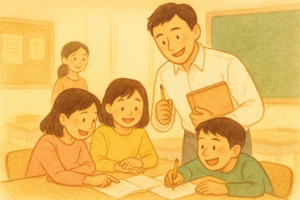
教科化の目的
文部科学省が掲げた道徳教科化の目的は次の三つです。
- 生命や人間の尊厳を理解し、主体的に判断・行動する力を育てる
- 社会の一員として、よりよく生きるための態度を養う
- 多様な価値観を認め合い、共に生きる姿勢を育む
これらは抽象的に見えますが、実際の授業では「家族」「友情」「正義」「命」「公正」「勤勉」などのテーマを通して、子どもたちの心を耕すことをめざします。
教科化で変わったこと
① 教材の選定と授業づくり
従来の読み物中心の授業から、話し合いやロールプレイなど、体験的・対話的活動が重視されるようになりました。
教材も文部科学省検定の教科書が導入され、内容の一貫性が確保されました。
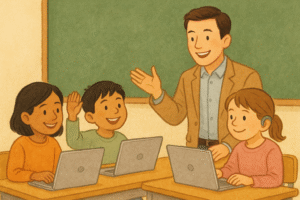
② 評価の導入
道徳にも「評価」が導入されましたが、数値評価ではなく文章による記述評価です。
「どんな考えをもち、どのように深めたか」を観点に記述します。
一方で、「心を数値化するのか?」という疑問や、評価作業の負担増を指摘する声もあります。
③ 校内体制と授業研究の活性化
道徳主任の配置や授業公開の推進により、学校全体で道徳教育を見直す動きが広がりました。
他教科の授業にも「道徳的価値」を関連づける意識が高まっています。
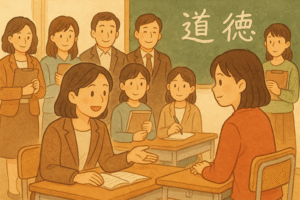
現場で感じる課題
1. 評価の難しさ
最も多くの教師が悩むのが「評価」です。
子どもの考え方に優劣をつけるわけにはいかず、個人の成長をどう捉えるかに悩みます。
評価を意識しすぎると、子どもが“正解を探す”ような道徳になってしまう危険もあります。
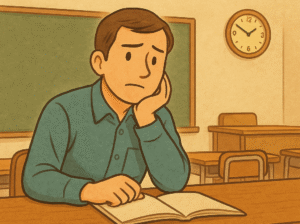
2. 教材の形式化
検定教科書の導入で教材が整った一方、テーマが抽象的で、子どもの実感とかけ離れていることもあります。
教師の工夫次第で「生きた道徳」にも「形だけの道徳」にもなってしまうのが現実です。
3. 授業時間の確保と多忙化
週1時間の道徳を確実に実施することは容易ではありません。
実際には行事や特別活動との兼ね合いで削られることも多く、内容の充実との両立が課題です。
教科化から5年:見えてきた成果と課題
実施から5年余りが経ち、現場では少しずつ変化も見えてきました。
良かった点
- 子どもたちが「考えを言葉にする力」が育ってきた
- 教師同士で授業を見合う文化が生まれた
- いじめや人権に関する対話の質が向上した
一方での課題
- 授業が“予定調和的”になりがち
- 評価が形骸化しやすい
- 教員の多忙化により、十分な指導準備が難しい
制度が変わっても、教師が子どもと真正面から対話する時間をどう確保するかが鍵となっています。
今後の道徳教育に求められるもの
これからの道徳教育に必要なのは、授業の質の向上です。
- 子どもの心の動きを丁寧に受け止める
- 一人ひとりの価値観を尊重し、押し付けない
- 教師自身も「道徳的対話の一員」として関わる
教科化によって問われているのは、教師自身の姿勢なのかもしれません。
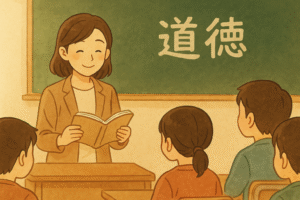
おわりに
「道徳の教科化」は、単なる制度変更ではありません。
それは、社会が「心の教育をどう位置づけるか」という問いへの答えでもあります。
正解がないからこそ、子どもとともに考え、悩み、語り合う。
その営みの中にこそ、本来の道徳教育の価値があると感じています。

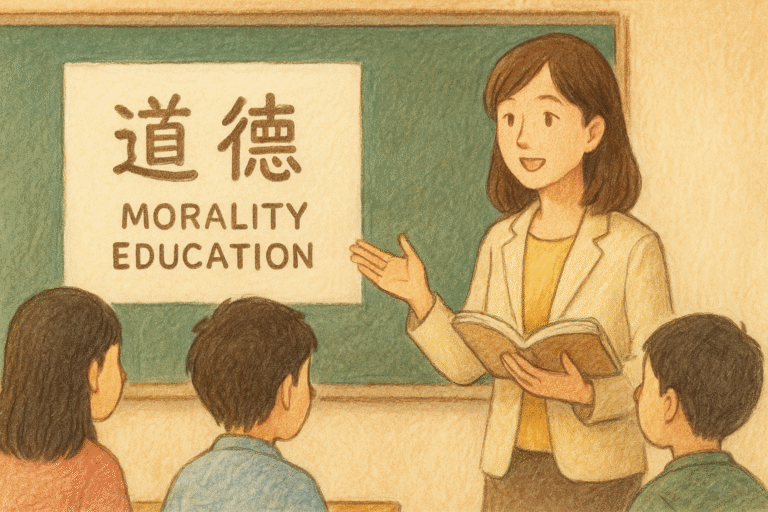
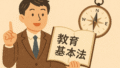
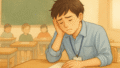
コメント