【40代教員の退職カウントダウン97:退職まで残り3年4ヶ月】
はじめに
前回の記事では、向山洋一と「教育技術の法則化運動」を紹介しました。
【教員の教養シリーズ:向山洋一と教育技術の法則化運動】
教育技術の法則化運動とは「良い授業のやり方をみんなで共有する」という考え方が、授業づくりを大きく変えた運動でした。
今回取り上げるのは、上越教育大学名誉教授・西川純氏が提唱した「学び合い」です。
私自身は10年ほど前にこの「西川式学び合い学習」に出会い、算数や社会科を中心にたくさんの実践にチャレンジしています。「西川式学び合い」もまた、私のみならず、多くの先生の従来の授業観を大きく揺さぶるものでした。
- 一斉授業をしても、全員を見きれない
- 個別指導に追われて毎時間ヘトヘト
- グループ活動をしても成果が見えにくい
今まさに、そんな悩みを抱える若手の先生にこそ、「学び合い」の考え方を知ってほしいと思います。
私は40代の小学校教務主任(担任兼務)で、2028年度末に退職予定です。
詳しくはこちら→【私が退職しようと決意した具体的経緯】
今回の記事では、10年以上にわたり現場で「学び合い学習」に取り組んできた立場から、その実践を現場目線で整理してみたいと思います。
なお、記事内で使用しているイラストは、実際の授業記録写真をもとに生成AIでイラスト化したものです。現場の雰囲気を感じながら読んでいただければ幸いです。
「学び合い」とは――一人も見捨てない授業観
西川純氏の「学び合い」は、「一人も見捨てない学び」を実現するための授業づくりです。
従来の授業では、教師が説明し、子どもが静かに聞き、分からない子が取り残される——そんな構図になりがちでした。
しかし、それだけではありません。
一斉授業の中では、教科書を読むだけで理解できる子どもや、少しの説明で分かる子どもにとっては、長い説明の時間が“退屈な待ち時間”になってしまうこともあります。いわゆる「浮きこぼれ層」です。
つまり、従来型の授業では「ついていけない子」と「待たされる子」の両方を生み出してしまうのです。
西川氏は、この前提そのものを根本から疑いました。
教師一人の力で40人全員を完璧に教えることはできない。だったら、子ども同士の力を活かせばいい。
この考え方こそが、「学び合い」の出発点です。
「学び合い」の3つの価値観
- 誰一人取り残さない クラス全員が課題を達成するまで授業を終わらせない。 「自分だけ分かればいい」から「みんなでできるようにしよう」へ、教室の空気を変える。
- 子どもの力を信じる 子どもには友だちを支え合う力がある。 教師は“全部教える人”ではなく、その力を引き出す環境づくりの専門家になる。
- 協働こそ本来の学び 暗記や一方通行の講義ではなく、子ども同士の対話と助け合いによる学びを重視する。
つまり「学び合い」とは、“教師が教える授業”から“みんなで学びをつくる授業”への転換を目指す実践です。
授業の基本構造――3つのステップ
「学び合い」の授業はとてもシンプルです。次の3ステップで構成されます。
① 目標を明確に示す(導入)
授業の冒頭で、教師が今日のゴールを具体的に示します。
- 「この資料を使って、日本の産業の変化を説明できるようにする」
- 「全員が“鎌倉幕府の成立理由”を説明できるようにする」
といった形で、子どもが自分でも達成を確認できる課題にします。
さらに、「クラス全員でこの目標を達成する」と伝え、全員達成を目標化します。
② 子ども同士の学び合い(展開)
離席を許可し、子どもたちは課題に向けて自由に動き出します。
- グループやペアは教師が決めず、自然に生まれる
- 分からない子は友だちに質問しに行く
- 分かる子は周りに声をかける
教師は講義するのではなく、教室内を歩きながら「どこで助け合いが起きているか」を観察します。
一人で悩む子がいても、すぐに手を出さず、まずは仲間の力を信じて見守ります。

③ 全員の到達をチェックする(まとめ・評価)
授業の終わりには、短い確認問題や発表活動で全員の到達状況を確かめます。
- 「できた子は先生のところにノートを持ってきて」
- 「全員が○をもらったら授業終了」
といった方法で、“一人も取り残さない”を可視化します。
誰かが理解できていなければ、クラス全体の課題として次に活かします。
実践例――中学校社会科「公民」の授業から
私が実践した中学校3年生の公民の授業で、「少子高齢化が社会に与える影響」をテーマにした学び合いの例を紹介します。
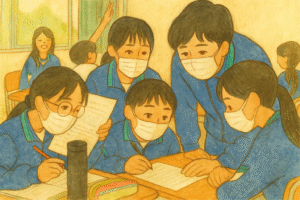
授業の流れ
- 導入(5分) 教師が黒板に次の目標を提示します。
> 「全員が“少子高齢化が日本社会にどんな影響を与えているか”を説明できるようになる」
さらに、「最後に一人ずつ説明チェックをする」と伝え、ゴールを明確にします。 - 学び合い(25分) 生徒たちは教科書や資料をもとに意見を出し合いながら話し合います。
「年金制度にどう影響する?」「労働力の減少って何?」など、対話が自然に生まれます。 教師は教室を歩き、グループの様子を観察。分からない子には「〇〇さんに聞いてごらん」と促すだけで、直接解説はしません。
良い資料に目をつけている生徒や説明が的確な生徒は、周りに聞こえるように即時評価をします。
理解が進んだ子や友達の説明に納得できた生徒が別のグループに説明に行く姿も見られます。 - まとめ・評価(10分) 最後に、グループに分かれて生徒一人ずつが1分間で「少子高齢化の影響」を他者にプレゼンします。
教師はあらかじめチェックしておいた気になる生徒の説明を確認に行きます。全員が要点を述べられたところで授業終了です。
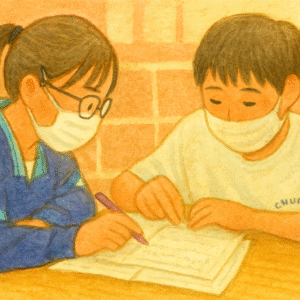
この授業では、私は一度も講義をしていません。
それでも、生徒同士の学び合いによって、全員がテーマを理解し、自分の言葉で説明できるようになっていました。
さらに、後の定期テストでも、一斉授業と比べて得点が下がることはなく、学習の定着も確認できました。
もっとも、これは2学期以降の実践であり、「学び合い」の良さやルールがしっかりとクラスに浸透してきた時期の様子です。1学期は、「なぜ学び合うのか」「どうすれば助け合えるのか」といった価値づけに時間をかける必要があります。
この段階になると、授業のまとめの場面でも自然に学び合いが生まれ、社会科が苦手な生徒へのサポートも学級全体で行われるようになります。
教師の役割は、資料準備と課題設定を行うことが中心となり、授業中に直接教える場面はほとんどありません。
この実践は、私が中学校教員として行ったものですが、小学校でも同様に効果を実感しています。
社会科はもちろん、算数や理科でも応用でき、特に算数では効果が顕著でした。私のクラスの算数テストは常に学年で最も高い得点率を記録していました。
学び合いの成果――教室の空気が変わる
実践校の報告では、次のような成果が多く見られます。
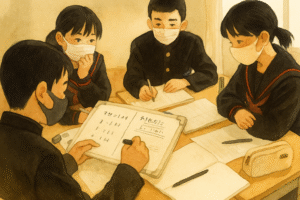
① 学力の“底上げ”
平均点よりも最低点が上がる傾向があります。
「できる子だけが伸びる」のではなく、クラス全体が底上げされます。西川氏は「平均点ではなく最低点を見よ」と強調しています。
クラスの“できない子”が確実に伸びることを大切にする姿勢です。
② 学びへの意欲と人間関係の変化
- 「分かった!」よりも「みんなでできた!」が喜びになる
- 「ありがとう」「教えてもらって助かった」という声が増える
- クラスに安心感が生まれ、発言や質問が増える
これにより、教室の雰囲気が競争的から協働的へと変わります。
不登校傾向の生徒が社会の時間だけ教室に戻ったり、学力境界値の生徒が笑顔で学習に参加したりする例もあり、“つながりのある学び”が生まれやすくなります。
また、人生において学力以上に重要だと思われる非認知能力、中でも援助要請スキルや他者と協力し合ってタスクを達成する能力が育まれます。
③ 教師の負担感が減る
「学び合い」を取り入れることで、教師は“すべてを一人で教え込まなくてはならない”というプレッシャーから解放されます。
「子どもの力を信じて待つ」という姿勢に変わることで、心にも大きな余裕が生まれます。
私自身、定期テストの結果を確認したときに、「もう全部を自分で教えなくてもいいんだ」と気づき、肩の力がすっと抜けたのを覚えています。
もちろん、最初は試行錯誤の連続でした。
しかし、クラスに「学び合い」の文化が定着してからは、授業準備の時間が大きく減り、授業中も子どもたちの様子を見守りながら採点や課題の点検などを並行して行えるようになりました。
「学び合い」は、単なる授業法ではなく、教師自身の働き方を変える実践でもあります。
子どもたちの“自分で学ぶ力”を育てることは、同時に教師に“心や時間の余裕”をもたらすことにもつながります。
私にとって「学び合い」は、まさにセルフ働き方改革でした。
「学び合い」の課題と注意点
① 「先生が教えないのは放任では?」
確かに、表面的に見ると“放任”に見えることがあります。
しかし「学び合い」の教師は、
- 明確なゴールを設定し
- 全員の到達を必ずチェックする という責任のある見守り役です。 「任せる」と「放任」は違います。
ここをまずは児童・生徒が、そして同僚、さらには保護者が理解する必要があります。当初はそのための説明を惜しんではいけません。
② 「できる子ばかりが教えるのでは?」
教師は、「教える側」「教えられる側」という固定的な関係が生まれないよう、声かけを工夫します。
私自身の実践から感じるのは、「できた子が他の子の理解を助けること」も、自分の学びを確かめる大切な機会になるということです。
つまり、“役割として教える”のではなく、“学びの循環をつくる”ことが大切なのです。
また、小学校では教科によって立場が入れ替わります。
算数では教えられる側だった子が、社会では説明する側に回る。体育では得意を生かしてリーダーになる。
こうした教科をまたいだ学び合いの実践が、学級全体の人間関係を豊かにし、クラスの一体感を育ててくれると実感しています。
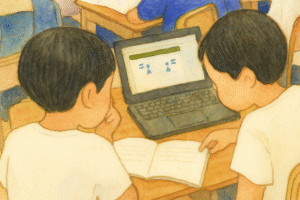
③ 「話せない子が孤立しないか」
実践の初期段階では、人とのコミュニケーションが苦手な低学力の子が、孤立しているように見えることがあります。
しかし、実際には「孤立している子が新たに生まれた」のではなく、これまで見えにくかった孤立が“見えるようになった”ということです。
大切なのは、学級全体で「どうすればみんなで学べるか」を考え、話し合いながら価値づけしていくことです。そのプロセス自体が、子どもたちの非認知能力の向上や学級の成長につながります。
つまり、孤立への気づきと対応そのものが「学び」なのです。
若手教師へのアドバイス――小さく始めよう
いきなり全授業を「学び合い」に変える必要はありません。
まずは1時間だけ、小さく試すことから始めてみましょう。
- 今日の目標を具体的に板書する
- 「全員でここまでできるようにしよう」と伝える
- 子ども同士で教え合う時間を5〜10分設ける
- 簡単な確認問題で全員達成をチェック
これだけでも、教室の空気が少し変わるはずです。
「教育技術の法則化運動」が“技術を共有する文化”を作ったように、「学び合い」は“子どもを信じる文化”を教室に生み出します。そして同時に教師の働き方改革にもつながると私は思っています。
おわりに
「学び合い」は単なる授業技法ではなく、教育観の転換です。
「子どもを信じるか」「教師一人で抱え込みすぎていないか」――その問いを、私たちに投げかけています。
もちろん、最初から完璧にはいきません。けれど、子ども同士が助け合い、教室全体で「できた!」を共有できたとき、その喜びは、どんな指導技術にも勝る“教育の瞬間”になります。
授業づくりに悩む若手の先生へ。
「子どもたちに任せる」授業観に出会うことが、教師としての新しいスタートになるかもしれません。

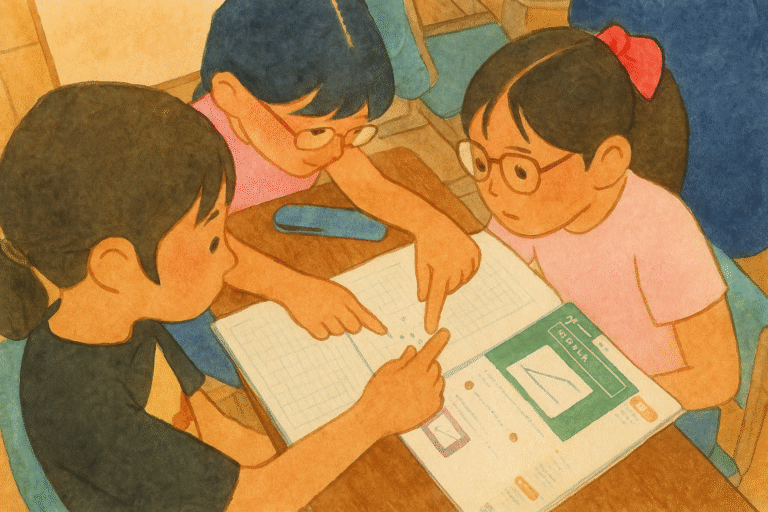

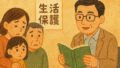
コメント