【40代教員の退職カウントダウン68:退職まで残り3年5ヶ月】
はじめに
「家賃は毎月払うものだから仕方ない」
「持ち家のローンは他の先生たちも結構な額 組んでいるから大丈夫」
そう思っていませんか?
実は、住居費こそ固定費の中で最大級の見直しポイントです。
月1万円下げるだけで年間12万円、30年で360万円。
家賃やローンは金額が大きいからこそ、少しの調整で人生に大きな余裕が生まれます。
私は40代小学校教務主任(担任兼務)、現在住宅ローンを抱えながらも2028年度末に正規教員を退職する予定です。
先生家庭と住居費の関係
教員という仕事は異動・転勤があるため、必ずしも「持ち家=正解」ではありません。
公務員宿舎や住宅手当などの制度をうまく活用すれば、家計への負担を大きく減らすことも可能です。
一方で、周囲の「そろそろマイホームを買わなきゃ」という空気に流されてしまうケースも少なくありません。
しかし、住宅購入は“感情”ではなく“数字と状況”で冷静に判断することが大切です。
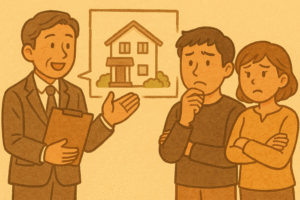
「教員は持ち家がいい?——住宅ローンの“借りやすさ”が生むメリットと落とし穴」
「教員夫婦でペアローンを組む前に知っておきたい5つの落とし穴」
🏫 教員の異動・転勤の仕組みは都道府県で異なる
教員の異動範囲は、都道府県や教育委員会の方針によって大きく異なります。
- 市内完結型:政令指定都市(横浜市・名古屋市・福岡市など)やそれに準ずる都市
→ 原則として市内のみの異動。生活基盤を変えずに勤務できる。 - ブロック型:愛知県・大阪府・広島県など
→ 採用地域の周辺市町村まで異動範囲。基本的には通勤圏内での異動が中心。 - 広域型:岐阜県・長野県・福井県など
→ 県全体で異動。市をまたぐ転勤が当たり前。
異動範囲が広い地域(ブロック型・広域型)では、持ち家がリスクになる可能性があります。
たとえば、通勤時間が片道1時間を超えるような異動も珍しくなく、
「せっかく家を買ったのに、平日は家にほとんどいない」というケースも実際にあります。
岐阜県に勤めている私の友人は、通勤に高速道路を使っているそうです。交通費もバカになりませんね。
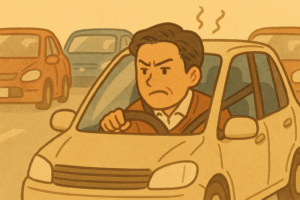
住居費を見直す方法3つ
1. 賃貸の場合
- 家賃交渉:相場より高ければ更新時に交渉可能。
- 引っ越し:家賃を1万円下げれば年間12万円。駅から少し離れる、築年数を下げるだけで大きな差。
- 勤務先に近づく:家賃が少し高くても、通勤時間や交通費を減らすほうが良い場合もある。
家賃交渉は「そんなことできるの?」と思われるかもしれませんが、家主にとって空室リスクは大きな負担です。そのため、家賃には十分に交渉の余地があります。
実際、私の友人は「周辺の相場では◯万円なので…」と具体的な金額を提示して交渉したところ、月額1万2千円の減額に成功しました。
また、家賃の値上げを拒否することも法律上可能です。
家賃は法律で「貸主と借主、双方の合意によって決まる」と定められており、貸主が一方的に値上げすることはできません。
値上げに反対したからといって強制退去させられたり、電気・水道を止められたりすることはありません。不合理な値上げは、はっきりと断って大丈夫です。(ただ、昨今のインフレから仕方ない値上げはあります。何でもかんでも断るというのは少し違うかなと思います)
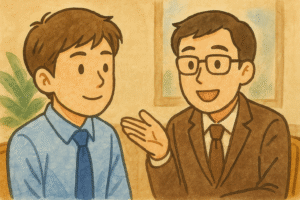
2. 持ち家(ローンあり)の場合
- 借り換え:他行借り換えで金利が下がれば数百万円単位で総返済額が減る。
- 利率交渉:固定金利を選択している先生は「他行の利率は◯%なので借り換えを検討しています」と具体的に交渉すると下がる場合がある。
- 売却→賃貸:都道府県によって転勤が多い先生は「持ち家が足かせ」に。住宅価格が上がっている地区では思い切った選択も。
私は固定金利で住宅ローンを組んでいたため、借り換えも視野に入れて金利の引き下げ交渉を行いました。
その結果、金利を1.55%から1.0%に下げてもらうことができ、毎月約8,000円の支出削減につながりました。
銀行は営利組織です。
教員は信用力が高く「優良顧客」とみなされるため、借り換えられるくらいなら金利を下げようという判断が働くことがあります。つまり、金利交渉には十分な余地があるということです。
3. 住宅を選ぶ際の指針
- 「住宅費=手取りの25%以内」が安心ライン。
- 家を購入するなら、売却の可能性も視野に「資産価値が落ちにくい家か?」を重視。郊外の新築より、駅近・中古リフォームの方がリセールしやすい。
私は妻とよく話し合い、「住宅よりも、思い出や日々の生活にお金を使いたい」という価値観のもと、中古住宅を購入しました。
夫婦ともに教員ということもあり、銀行からは高額のローンを組むことが可能でしたが、提示された上限額よりもかなり低い金額で住宅ローンを組みました。
その結果、月々の返済負担を抑えることができ、その分を投資に回したり、妻が教員から転職を決断する際の精神的な支えにもなりました。
15年以上住んでいますが、中古住宅であることに不満や不便を感じたことはありません。
また、新築住宅と違い、中古住宅は購入後の価格下落が比較的緩やかです。
近年の住宅価格高騰もあり、昨年あらためて我が家の資産価値を確認したところ、購入時とほとんど変わらない金額でした。
もし今売却したとすれば、15年以上ほぼ家賃を払わずに暮らせた計算になります。
こうした経験からも、リセール(再販売)価値の高い家を選ぶことは非常に重要だと感じています。
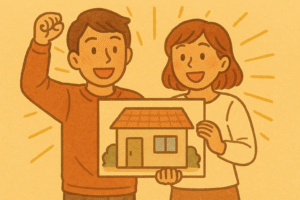
ケース別シミュレーション
- 例1:家賃8万円→7万円に交渉成功
→ 年12万円の固定費削減。浮いたお金をNISAで積立投資。 - 例2:3,000万円ローン、金利1.5%→0.8%に借り換え
→ 総返済額が約300万円減。 - 例3:マイホーム購入を見送り、賃貸+資産運用
→ 住居費を柔軟に抑え、転勤にも対応できる。
よくある疑問Q&A
Q. 家は資産になるから買った方が得では?
A. 場所や条件によります。売却できない家は「資産」ではなく「負債」になり得ます。
Q. 引っ越しは手間や費用がかかるのでは?
A. 初期費用はかかりますが、条件のいい物件への住み替えなら数ヶ月〜1年で回収できるケースも多いです。
Q. 子どもの教育を考えると、早めに家を買った方がいい?
A. 学区や立地を理由に買うのはあり。ただし「教育費と住宅費の両立」が苦しくならないか必ず試算を。
まとめ
- 住居費は「固定費の王様」。少し動くだけで数十万〜数百万の効果。
- 賃貸なら交渉・引っ越し、持ち家なら借り換え・繰上げ返済を検討。
- 「資産になる家かどうか」「生活水準を圧迫していないか」を冷静に判断する。
- 浮いたお金は生活防衛資金と投資へ。
固定費を見直して投資資金を生み出そうシリーズ
「教員のための「貯める力」入門 ― 生活満足度を落とさず、毎月5万円をひねり出す方法」
「固定費見直しシリーズ① ― 通信費を見直せば、月5,000円はすぐ浮く」
「固定費見直しシリーズ②― 保険の整理だけで月1〜2万円が浮く」
「固定費見直しシリーズ③ ― サブスクを整理して“自動出費”を止めよう」
「固定費見直しシリーズ④ ― 住居費を整えると家計は一気に軽くなる」
「教員は持ち家がいい?——住宅ローンの“借りやすさ”が生むメリットと落とし穴」
「教員夫婦でペアローンを組む前に知っておきたい5つの落とし穴」
「固定費見直しシリーズ⑤― 車のコストを整えると数百万円の差になる」
「車の残価設定ローンは本当にお得? 教員家庭が避けるべき“資産を減らす仕組み”」


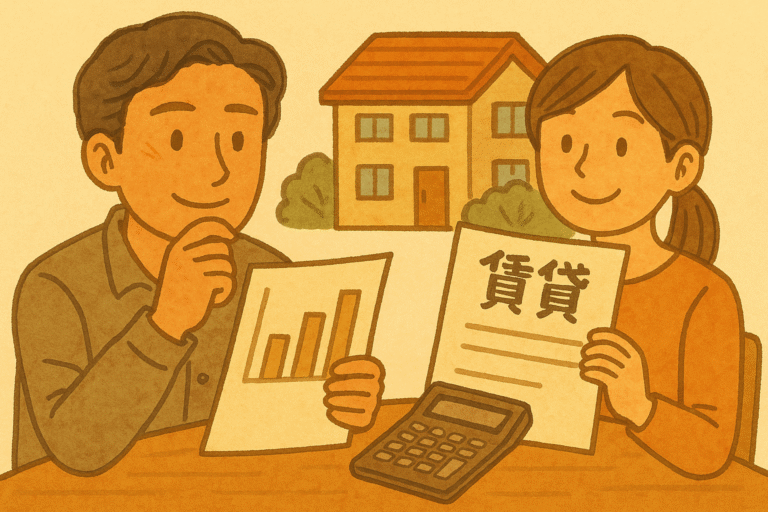
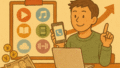

コメント