【40代教員の退職カウントダウン69:退職まで残り3年5ヶ月】
はじめに
教員として働いていると、同僚の多くが「マイホームを購入している」ことに気づく場面があると思います。
全国的には持ち家率は約6割前後ですが、教員は安定した収入や身分からローン審査に通りやすく、持ち家率は高い傾向にあります。
例えば北海道恵庭市の調査では、教職員の持家率は72%という数字も出ています。
しかし、だからといって「教員なら家を買うのが正解」とは限りません。むしろ安定した属性が“借りすぎのワナ”を生むケースも多く、慎重な検討が必要です。
この記事では、教員だからこそ知っておきたい教員ならではの住宅ローンのリスクを整理します。
私は40代小学校教務主任(担任兼務)、2028年度末に正規教員を退職する予定です。
詳しくはこちらの記事から→【私が退職しようと決意した具体的経緯】
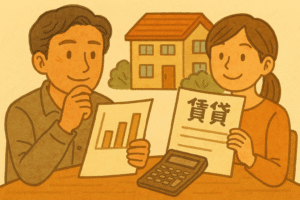
住宅ローンにおける教員の“属性の良さ”は武器にもワナにもなる
メリット(武器)
- ローンが通りやすい
教員は安定した収入と身分から金融機関の評価が高く、金利優遇や借入枠が広がることが多いです。 - 勤続年数の信用
長期勤務が前提と見なされやすく、同じ条件でも他業種より有利に借りられることがあります。
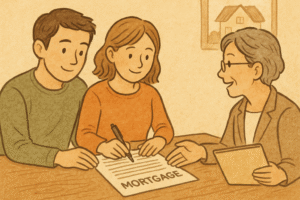
デメリット(ワナ)
- 借りすぎてしまう
銀行が提示する「借入可能額=返済可能額」ではありません。
私の友人に、夫婦ペアローンで6千万円以上の住宅ローンを組み、家計が火の車だと言っていた教員夫婦がいます。
年収の8倍まで借りられると言われますが、現実的には手取りの20〜25%以内に抑えないと家計を圧迫します。 - 異動・転勤のリスク
異動や転勤がある職種だからこそ、住宅ローンによる持ち家購入は柔軟な住み替えを妨げる可能性があります。特に岐阜県や長野県など人事異動が広域にわたる教育委員会に所属している先生は注意が必要です。 - 維持費が続く
見落とされがちですが、持ち家にはローン以外にも固定資産税や保険料、修繕費などの維持費がかかります。
屋根や外壁の塗装、給湯器の交換など、年数とともに高額なメンテナンスも必要です。
マンションなら管理費や修繕積立金、駐車場代も発生します。持ち家は「買って終わり」ではなく、住宅ローン以外の「持ち続けるコスト」が意外と大きいのです。
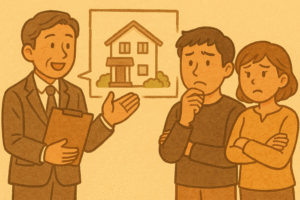
賃貸と持ち家の損得を比べる視点
- 購入総コスト:頭金+諸費用+ローン利息+税金+修繕費-売却価格
- 賃貸総コスト:家賃+更新料+火災保険+引っ越し費用
- 柔軟性の価値:異動・学区変更・家族構成の変化に合わせられる自由度
- 通勤時間のコスト:片道20分短縮=月13時間分の時間を得る価値
お金だけで考えると、ほとんどの物件は「負債」に近くなりやすいのが現実です。購入時点から資産価値が下がる物件が多いためです。
教員ならではの購入チェックリスト
- 返済比率は手取りの20%以内(上限でも25%まで)
- 維持費を“第二のローン”と考える(固定資産税・修繕費・管理費)
- 異動先からの通勤可能性を確認
- 出口戦略を持つ(貸せるか・売れるか・相場はどうか)
- 生活防衛資金+毎月の投資は死守(家のために資産形成を止めない)
よくある誤解
- 「ローン完済後は住居費ゼロ」→固定資産税・修繕は一生続きます
- 「土地は必ず資産になる」→買値を上回る価格で売れなければ負債
- 「老後は賃貸を借りられない」→住宅余りの進行で高齢者可の物件は増加中。資産があれば選べます
まとめ:先生にとっての最適解は?
- お金の自由度を優先するなら賃貸ベースがおすすめ。
- 資産性の高い物件に出会えた時のみ購入というのが安全な選択。
- 教員はローンを借りやすい=メリットだが、借りすぎが最大のリスク。
- 資産形成の面から言うと「買えるから買う」のではなく、「買っても投資や貯金を続けられるか」で判断することが大切です。
固定費を見直して投資資金を生み出そうシリーズ
「教員のための「貯める力」入門 ― 生活満足度を落とさず、毎月5万円をひねり出す方法」
「固定費見直しシリーズ① ― 通信費を見直せば、月5,000円はすぐ浮く」
「固定費見直しシリーズ②― 保険の整理だけで月1〜2万円が浮く」
「固定費見直しシリーズ③ ― サブスクを整理して“自動出費”を止めよう」
「固定費見直しシリーズ④ ― 住居費を整えると家計は一気に軽くなる」
「教員は持ち家がいい?——住宅ローンの“借りやすさ”が生むメリットと落とし穴」
「教員夫婦でペアローンを組む前に知っておきたい5つの落とし穴」
「固定費見直しシリーズ⑤― 車のコストを整えると数百万円の差になる」
「車の残価設定ローンは本当にお得? 教員家庭が避けるべき“資産を減らす仕組み”」


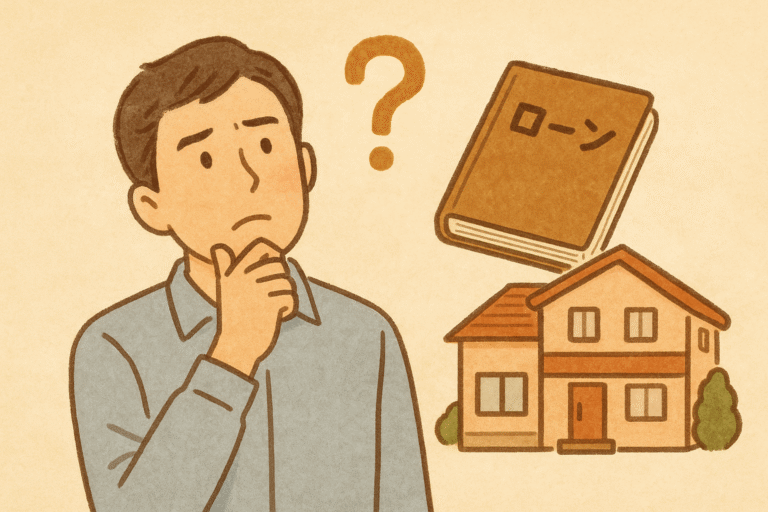

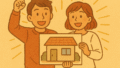
コメント