【40代教員の退職カウントダウン59:退職まで残り3年5ヶ月】
はじめに
前回の記事では、私のクラスで取り組んだ実践例を中心に「外国籍児童とどう向き合うか」をお伝えしました。
「日本に増える外国籍児童生徒と学校現場の対応 ~もう一つの特別支援教育~」
今回はその続編として、全国的なデータや報告された事例を踏まえ、外国籍児童生徒が増える現状と、学校が直面する課題・対応策を整理します。
私は40代小学校教務主任(担任兼務)で、2028年度末に正規教員を退職予定です。
詳しくはこの記事をどうぞ→【私が退職しようと決意した具体的経緯】
これまで多国籍の児童を担任してきた経験と教務主任という立場から、「現場目線」を意識してまとめました。

外国籍児童生徒の増加と背景
文部科学省の統計によると、公立学校に在籍する外国籍児童生徒は2012年の約7万人から2023年には約13万人へと倍増しました。特に愛知、神奈川、東京、大阪などの都市部で増加が顕著です。
2012年には約3万3407人だった日本語指導が必要な児童生徒数は、2023年には約2倍になり、こうした児童生徒が在籍する学校は約1万3000校に上ります。
全国的に日本語での学習や生活に困り支援を必要とする児童は増加しているということです。
背景には以下の要因があります。
- 技術者や技能実習生など外国人労働者の増加
- 家族帯同の広がり
- 国際結婚や帰国児童の存在
先生方もコンビニエンスストアやチェーン店で働く外国籍の方や道ゆく観光客ではない外国籍の人が増えたように感じませんか?もはや日本経済は外国人なしでは回っていかない、そういう識者もいます。
また、外国籍の子どもたちは「短期滞在」「永住予定」など滞在目的もさまざまで、日本語能力、親の教育への意識も様々です。学校現場は一律の対応ではなく個別の調整や配慮が欠かせません。
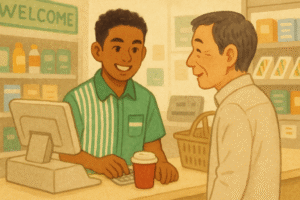
宗教面での配慮が必要な例
実際に報告されている配慮が必要なケースを紹介します
礼拝と祈りの場
イスラム教徒の子どもは1日に5回の礼拝を行います。学校によっては空き教室を祈りのスペースにしたり、部活動を早退して家族と祈る、金曜日の午後は休んで良いなど、柔軟な対応が求められます。
食事と給食
豚肉や牛肉、アルコール由来の食品を避ける必要があります。給食は弁当併用や特別メニュー、修学旅行ではイスラム・ヒンドゥ対応食を用意するなど、学校と保護者の連携が重要です。
ラマダーン(月)断食
断食中は体育参加の可否や給食時間の過ごし方を保護者と相談し、個別対応をとる必要があります。
服装や体育授業
ヒジャブの着用や肌を隠す体育着、水泳を見学するケースなど、文化的背景を尊重する工夫が必要です。

日本固有の学校文化とギャップ
上履き・土足厳禁
海外では土足が当たり前の国が多く、日本特有の上履き文化は戸惑いの原因になります。丁寧な説明とサポートが欠かせません。
掃除・片づけ文化
児童自身が掃除をする文化は、外国籍家庭にとって理解が難しい場合があります。私自身も「なぜ子どもに召使のようなことをさせるのか?」と問われた経験があります。「協力や責任感を育てる教育の一環」であることを説明すると納得してもらいやすいです。
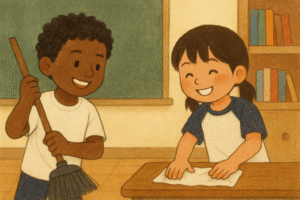
給食の共食文化
日本では給食をクラス全員で同じものを食べますが、海外では弁当やカフェテリア方式が一般的という国もあります。文化的な違いを説明し、必要に応じて弁当持参を認めることが大切です。
コミュニケーションと言語支援
- 保護者対応では通訳や翻訳アプリ、多言語資料を活用する必要があります。
- 難しい日本語は避け、短文・平易な言葉で説明しなければ伝わりません
- 重要事項はジェスチャーなど視覚的に示し、誤解を減らす工夫をする必要もあるでしょう
ただし、文化によってジェスチャーの意味が異なるため、注意が必要です。例えば日本の手招きは、欧米では正反対の「あっちへ行け」を意味する場合があります。
また、「頭をなでる」は日本では褒める時に使うポジティブなものですが、東南アジアでは子ども相手でも失礼にあたる場合があります。
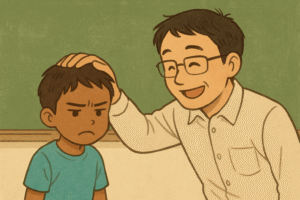
全国で発生した実際のトラブル事例
- 豚肉禁止を知らずに給食を提供 → 知らずに食してしまった
- 礼拝スペースがなく、教室で祈ってからかわれ、いじめ案件に
- 半袖短パンを強制し、宗教的理由で女子生徒が体育に参加できず不登校のきっかけに
- 行事の意味を保護者が理解できず、運動会や合唱祭を欠席。学校とのトラブルに
これらは知識不足や説明不足から起こります。解決には「宗教や文化の背景理解」と「丁寧な対話」が不可欠です。
学級担任や管理職が意識すべきポイント
- 家庭背景を入学時に把握する
- 宗教・食事・服装・行事について保護者と相談する
- 日本の学校文化を丁寧に説明する
- 食事・行事対応は学校全体で共有する
- 日本語支援や通訳を積極的に活用する
- 学級全体で異文化理解教育を進める
- トラブルは早期に対応し、外部の専門家とも連携
- 地域の多文化共生センターやNPOと協力する
いずれにしても外国籍児童の対応はとても大変です。担任一人が抱え込むのではなく、特別支援教育コーディネーターや管理職とともに対応を検討していくことが大切です。

まとめ
外国籍児童生徒の増加は日本の学校にとって大きな変化です。宗教や文化、生活習慣の違いは摩擦の原因にもなりますが、もはや受け入れなければならない流れです。
担任としてできることは、子ども一人ひとりの背景を理解し、保護者や学校全体と協力して柔軟に対応すること。こうした積み重ねが、多文化共生を実現する教室づくりにつながります。
合わせて読んでほしい シリーズ特別支援教育
「特別支援学級ってどんなところ?担任を経験した私がしんどさを解説」
「特別支援教育を理解したい!特別支援学級の担任におすすめの本3選」
「特別支援学級に入ると進路は閉ざされる? 〜ASDと知的障がいの進路のリアル〜」
「日本に増える外国籍児童生徒と学校現場の対応 ~もう一つの特別支援教育~」




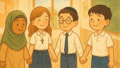
コメント