【40代小学校教員の退職カウントダウン54:退職まで残り3年6ヶ月】
はじめに:教員は税金に触れる機会が少ない
「あなたは去年いくら稼いで、いくら税金や社会保険料を払いましたか?」
すぐに答えられる先生は少ないのではないでしょうか。
教員は確定申告をする必要がなく、年末調整もすべて事務職員さんがやってくれるから仕方ありません。だから、自然と税金に触れる機会が少なく、「気づいたら引かれている」という感覚になってしまいます。いや、税金を引かれている感覚がない先生もいらっしゃるでしょう。
しかし、自分がいくら稼ぎ、どれだけ公的に負担しているのかを知らなくて大丈夫でしょうか?資産形成の基本は収入を知り、支出を把握することから始まります。
私は40代小学校教務主任(担任兼務)、2028年度末に正規教員を退職予定です。
詳しくはこの記事をどうぞ→【私が退職しようと決意した具体的経緯】
今回は、私自身の2024年度の数字を例に、支払った税金と社会保険料の総額を具体的に紹介します。ご自身の財産や資産運用について考えるきっかけとなれば幸いです。

【実例】私の年収と支払い総額
まずは結論から。
採用22年目で40代半ばの教務主任の、昨年度の給料総支給額は約777万円でした。
これがいわゆる私の年収です。
教員給与に関してはこちらの記事で解説
「教員給与の現状・将来見通しと他業種との比較(2025年時点)」
それに対して税金や社会保険料など「公的に払わなくてはならない支出」は約229万円と算出しました。
- 年収(給与収入額):777万円
- 支払った税金+社会保険料+その他公的負担:229万円
つまり、約3割弱は税金や社会保険料で消えている計算です。思ったよりも取られている印象はありませんか?
12か月働いても、実質4か月分の給料は国や自治体に支払っているのですね、、、
次は支払いの内訳を確認してみましょう。

所得税:国に払う税金
お給料に応じて払う国税です。「累進課税」で、収入が増えるほど税率が上がります。
我々教員の給料のレンジで言うと多くの先生が20%〜23%程度になるはずです。
ただ、777万円×20%ではありません。課税所得×20%です
- 年収から「給与所得控除(教員の必要経費のようなもの)」や「各種控除(扶養・生命保険など)」を引いた金額を課税所得と言います。
年収全部に税金かけるのは流石に可哀想だから「少しサービスするよ」と言う国の優しさでしょうか - この課税所得に累進課税の税率をかけて計算します。
私の場合は年間で約22万円が所得税として引かれていました。
住民税:県や市に払う税金
住民税は「前年の収入」に応じてかかる税金です。
- 市町村に約6%
- 都道府県に約4%
あわせて「収入の10%程度」を支払います。
私の場合は、年間で約28万円でした。
私の場合、ふるさと納税を活用しているので住民税は多くの先生よりも少ないと思います。
ただ、実際は少ないわけではなく、前払いをしているだけです。
ふるさと納税について詳しく知りたい方はこちらの記事へ
「やらない理由が見つからない!教員こそふるさと納税を活用しよう」

社会保険料:実は税金より重い負担
給料から自動的に天引きされるのが社会保険料です。私の実例です。
- 健康保険:約39万円(医療費の自己負担を軽減するために支え合う保険)
- 厚生年金:約77万円(将来の年金の資金として給与やボーナスから天引きされるお金)
- 介護保険:約8万円(介護が必要になった高齢者を社会全体で支えるため、40歳以上の国民が納めるお金)
👉 合計124万円
現在では、税金よりも社会保険料のほうが大きな負担になっています。
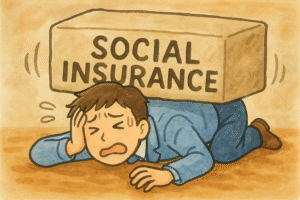
消費税や固定資産税など「見えにくい支払い」
給料から直接引かれるわけではありませんが、生活の中で確実に支払っているものがあります。
- 消費税(生活費・娯楽費 約400万円で計算):約38万円
- 固定資産税・都市計画税(持ち家):約12万円
- 自動車関連税(自動車税・重量税・自賠責保険):約5万円
- たばこ税や酒税、ガソリン税など:私自身はタバコやお酒をやらず、電気自動車でガソリンを使用しないので0円としておきます。先生方の中には重い負担となっている人もいるでしょう。
👉 合計で年間約55万円。
「見えにくい支払い」も積み重なると大きな額になります。
なお、退職時には退職金の税金を考える必要があります。退職金にかかる税金に関してはこちらの記事で→「退職金にかかる税金を計算してみよう【教員向け完全ガイド】」
トータルでどれくらい払っているのか?
すべてを合計すると──
- 税金(所得税・住民税・消費税・固定資産税など):約105万円
- 社会保険料:124万円
👉 合計約229万円/年
年収777万円でも、実際に使える金額は約550万円です。
この550万円の中で住宅や車のローン、基本的な生活費、通信費、娯楽費を支払い、さらに将来のための貯金をしなければいけません。
最近家計に少し余裕が出てきましたが、若い頃は本当にギリギリでした。
今後どうなる?増え続ける社会保険料
今後、少子高齢化の進展により社会保険料の負担はさらに増えると予想されています。
また増税の話題はつきません。
将来的に年収に占める税金や社会保険料の割合は今よりも大きくなっていくと考えられます。
教員は副業や節税の手段が限られているため、ふるさと納税やNISAなどの制度を理解し、上手に使うことが不可欠になってきます。
ふるさと納税については→「やらない理由が見つからない!教員こそふるさと納税を活用しよう」
NISAについては→「教員と相性抜群の投資制度?新NISAをわかりやすく解説」
まとめ:まずは「自分のお金の流れ」を知ろう
- 税金よりも社会保険料のほうが大きい
- 年収780万円あっても手取りは550万円程度
- 消費税・固定資産税などの「見えにくい負担」も無視できない
教員は普段、税金に触れる機会がほとんどありません。しかし数字で見える化すると、その負担の大きさが実感できます。実感すれば節税に対する意識や、行政サービスに対する意識も変わってくるかもしれません。
まずは「自分のお金の流れ」を知ること。そこから将来の家計防衛や資産形成を考える第一歩が始まります。まずは給料明細を眺めるところから初めてみませんか?もっと詳しく知りたいのであれば、この本がおすすめです。
合わせて読みたい:教員の資産形成シリーズ
「インデックス投資とは?投資初心者の教員にもおすすめの理由を徹底解説」
「投資で儲けるってどういうこと?投資でお金を増やすカラクリをやさしく解説」


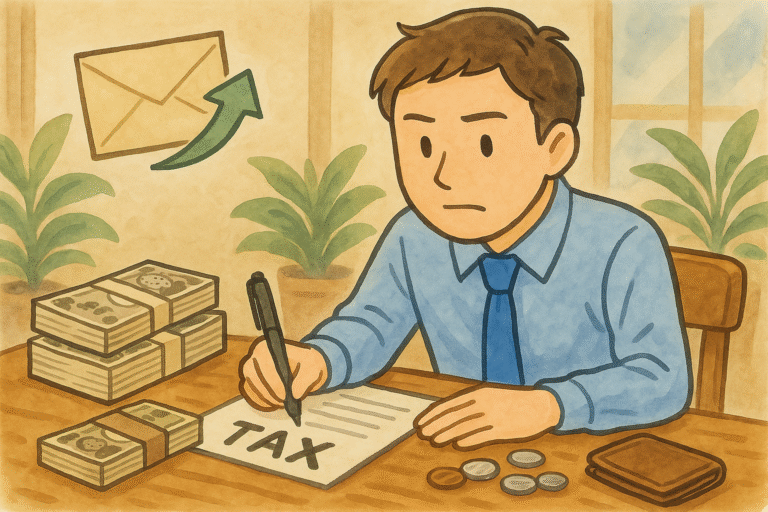


コメント