【40代教員の退職カウントダウン57:退職まで残り3年6ヶ月】
はじめに
「特別支援学級に入ると進路がなくなるのでは?」
「就職できなくなるのでは?」
こうした声を、保護者や先生から聞くことがあります。私自身、小中学校の特別支援学級担任を経験し、通常級から支援学級へ、また支援学級から通常級へと転籍を勧めたり受け入れたりした経験があります。
その中で感じたのは、多くの人の特別支援教育に対する理解不足でした。それは保護者のみならず多くの先生方にも感じました。
実際には逆で、本人の特性に合わない環境(通常級)に無理をして在籍する方が、不登校や孤立につながり、結果的に不利になる場合もあります。進路は支援学級に入るかどうかではなく、本人に合った学びの場で力を伸ばせるかどうかで決まります。

私は40代小学校教務主任(担任兼務)、2028年度末に正規教員を退職する予定です。
詳しくはこの記事をどうぞ→【私が退職しようと決意した具体的経緯】
私は今まで、小学校1年生から中学3年生までと小中両方の特別支援学級を担任しました。
今回は私が中学校で特別支援学級の進路指導をした際に集めた情報を元に、特別支援学級の進路選択について情報提供をします。特別支援の担任の先生だけでなく、通常学級の先生も知っておくべき内容だと思います。
ASD(自閉スペクトラム症)とは
- 特徴:コミュニケーションや対人関係の難しさ、興味・関心の偏り、こだわり行動が見られる。
- 知能の幅:知的水準は高い場合から低い場合まで幅広い。中には平均以上の学力を持つ生徒も少なくない。
- 学校生活での課題:対人関係のトラブルや集団活動の負担が大きくなりがち。ただし得意分野に強みを発揮するケースも多い。
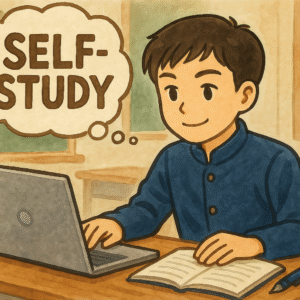
知的障害とは
- 特徴:知的機能の遅れに加えて、日常生活能力(読み書き、計算、社会生活スキルなど)の獲得に支援を必要とする。
- 分類:軽度・中度・重度など程度によって必要な支援や進路は異なる。
- 学校生活での課題:学習進度がゆるやかで、一斉授業よりも個別支援や実生活に直結する学習が効果的。
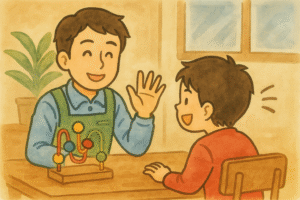
障害者手帳について
進路や就労を考える上で「障害者手帳」を取得するかどうかは大切なポイントになります。手帳を持っていることで、学校生活や就職活動、福祉サービス利用の場面で支援を受けやすくなるからです。手帳には大きく分けて3種類があります。
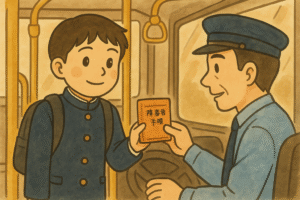
- 療育手帳(知的障害者用)
知的障害がある人を対象に交付される手帳です。障害の程度に応じて「A」「B」などの区分があり、医療費助成や交通機関の割引、就労支援サービスの利用につながります。特別支援学校進学や福祉的就労の場面でも活用されます。 - 精神障害者保健福祉手帳
発達障害(ASDやADHDなど)やうつ病などの精神疾患がある人が対象です。こちらも等級(1級〜3級)があり、雇用の場面で障害者雇用枠を利用したり、税金の控除や公共料金の割引を受けられる場合があります。
手帳を持っていると、受験の際に特別な配慮(イヤーマフの使用や別室受験等)が受けられることがあるので、発達障害のある生徒が高校や大学進学後に取得を検討することもあります。 - 身体障害者手帳
視覚・聴覚・肢体不自由など身体機能に障害がある場合に交付される手帳です。今回の記事のテーマであるASD・知的障害には直接は関係しませんが、同時に身体障害を持つ子どももいるため、学校では重複して使われることもあります。
👉 手帳は「必ず取らなければならないもの」ではなく、本人や家族が必要と判断したときに申請できます。ただし、取得しておくことで利用できる支援や制度の幅が広がるため、進路を考える上では大きな助けになるケースが多いです。
ASDと知的障害、それぞれの進路の違い
ASDの場合
- 学力が高いことも多く、普通高校や通信制・定時制高校への進学がよく見られる。
- 高校卒業後は専門学校・大学進学や一般就労に進むケースもある。
- ただし、人間関係や生活リズムでつまずきやすいため、サポート体制の有無が大きなカギになる。通信制高校へ通うためのサポート校という学校もあるが、2つの学校に所属することになるので学費が高額になる。
知的障害の場合
- 特別支援学校高等部への進学が中心。
- 特別支援学校は高校卒業資格を得ることはできない。
- 卒業後は一般就労が約3割、福祉的就労が6割以上。
- 「働いて稼ぐ」よりも「支援を受けながら社会参加を続ける」という形が多い。
福祉的就労とは?
特に知的障害のある生徒の進路先として大きな割合を占めるのが、就労継続支援A型・B型の福祉就労です。
- 就労継続支援A型
企業との雇用契約を結び、最低賃金以上の給与が支払われる。
「支援を受けながら働き、一般就労につなげる」ことを目標とする。 - 就労継続支援B型
雇用契約は結ばず、作業に応じて「工賃」が支払われる。
平均月収は数万円程度だが、体力や障害の程度に応じて無理なく働き続けられる場として重要。
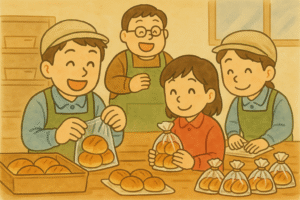
どちらも「働ける力はあるが、すぐには一般就労が難しい人」のために用意された制度です。単なる“受け皿”ではなく、社会参加を支える大切な仕組みだと理解しておくことが大切です。
先生に伝えたいこと
支援学級に入ることは、決して「進路の終わり」ではありません。
むしろ、本人に合った環境で学び、得意を伸ばしながら将来につなげるスタートラインです。
担任として進路に関わる際は、
- ASDと知的障害で進路の考え方が大きく異なること
- ASDの生徒は適切な支えがあれば、通常級の生徒と変わらない進路選択があるということ。手帳などの公的サポートの道も開けること
- 知的障害の生徒は支援学校高等部の進学によって生活力や社会性を身につけることができるということ
- その先にも福祉的就労を含めた多様な選択肢があること
を押さえておくことが、生徒や保護者に安心感を与えます。
合わせて読みたい:特別支援教育を理解しようシリーズ
「特別支援学級ってどんなところ?担任を経験した私がしんどさを解説」
「特別支援教育を理解したい!特別支援学級の担任におすすめの本3選」
「日本に増える外国籍児童生徒と学校現場の対応~もう一つの特別支援教育~」

まとめ
- 「支援学級に入ると進路が閉ざされる」は誤解。
- ASDの生徒は学力を生かして進学・一般就労の道が多く、知的障害の生徒は特別支援学校から福祉的就労につながることが多い。
- 福祉的就労(A型・B型)は就職の代替ではなく、「社会参加を支える仕組み」である。
本人にとって最も安心でき、力を発揮できる環境を選ぶことこそが、進路選択の第一歩です




コメント