【40代教員の退職カウントダウン41:退職まで残り3年6ヶ月】
はじめに
「特別支援学級の担任は人数が少ないから楽そう」
そう思っていませんか?
私は22年間の教員生活で、小学1年生から中学3年生まで幅広い学年を担任してきました。
その中で特に大変だったと感じたのが、特別支援学級を受け持ったときです。もちろん、どの学年も大変さはありますが、精神的にも肉体的にもつらかったのは特別支援学級の担任経験で、間違いなくトップ3に入るしんどさです。
私は現在40代の小学校教務主任(担任兼務)で、2028年度末に正規教員を退職予定です。
詳しくはこちらの記事へ→【私が退職しようと決意した具体的経緯】
この記事では、特別支援学級の担任として直面する“しんどさ”を、私の体験談を交えてお話します。これから特別支援学級を担任する先生や、興味を持っている方の参考になれば幸いです。

特別支援学級とは?
特別支援学級は、知的障害、発達障害、視覚・聴覚障害、肢体不自由など、多様な障害を持つ子どもたちが通う少人数クラスです。

「少人数だから個別に対応しやすい」というメリットもありますが、その分、一人ひとりに応じた配慮や対応が求められるため、通常学級とは違った大変さがあります。
加えて、担任は授業だけでなく、個別の支援計画作成や外部機関との連携、保護者との丁寧なやりとりなど、通常学級では経験しにくい仕事を担うことになります。
しんどさ1:子どもの成長が見えにくい
通常学級では、
- 漢字が書けるようになった
- 跳び箱を飛べるようになった
- 計算が速くなった
といった成長を目に見えて実感できます。教師にとって、子どもの成長を日々感じられるのは大きなモチベーションです。
しかし、特別支援学級ではそうはいきません。子どもの特性によっては「昨日できたことが今日はできない」「同じ課題を毎日繰り返す」ことも多くあります。
私自身、「果たして自分の指導は本当に役立っているのか?」と自問自答する日々でした。成長は確かにあるのですが、それがあまりに小さく、気づきにくいのです。
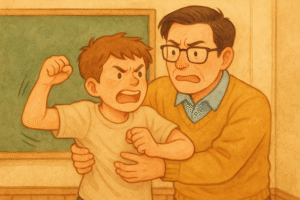
👉 ポイント:小さな変化を見逃さない観察眼と、成長を信じ続ける忍耐力が不可欠です。
しんどさ2:職場の理解が得られにくい
特別支援学級に対する周囲の理解は、残念ながらまだ十分とは言えません。
同僚に悪意があるわけではないのですが、
- 学年行事等の連絡や情報共有が後回しになる
- 「支援学級は人数が少ないから楽でいいよね」と誤解される
といったことは、現場で何度も経験しました。
管理職によっては、学級経営力の低い先生を特別支援に当てておけばよいという誤った認識を持っている人もいます。
しかし実際には、個別の支援計画や合理的配慮の検討、個別カリキュラムの作成など、通常学級にはない業務が山積みです。また、個別最適な支援というのは本当に難しいです。
それを知らない先生から「人数が少ないんだから余裕あるでしょ」と言われると、本当に嫌な気持ちになりました。
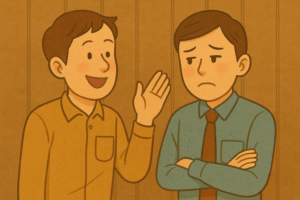
また、他教科の先生から「先生、そこはきつく叱らなきゃ!甘やかしてはだめですよ。」とよく言われました。通常級の子と同じ指導が効果的であるとは限らないのに、です。
叱責しないことが、甘やかしているように見えるのは特別支援教育への理解不足でしょう。
👉 ポイント:職場での情報共有を意識的に増やし、特別支援教育の実態を周囲に理解してもらう工夫が必要です。
しんどさ3:保護者対応の難しさ
特別支援学級の担任で最も大変だったのが保護者対応です。
子どもに障害がある場合、保護者の方も同じ特性を持っているケースがあります。そのため、
- 子どもの配慮内容をどう説明するか
- 支援の必要性をどう理解してもらうか
が非常に難しくなることがあります。
もちろん、障害を理解し、協力的にサポートしてくださる保護者も多くいます。しかし、障害特性を受け入れきれず、学校に過剰な要求をされる方もいます。子どもの特性に無関心で、学校で面倒さえみてくれればいいというスタンスの方もいました。
そうしたときの対応は、担任として大きなストレスでした。

👉 ポイント:保護者との信頼関係づくりは特別支援学級担任の最重要課題。スクールカウンセラーや管理職との連携も不可欠です。
しんどさ4:自分の知識と経験の不足
私は特別支援学級を担任する前は、通常学級での経験しかありませんでした。そのため、障害特性や支援方法に関する知識が不足しており、
- 本来は優しく接するべき場面で厳しくしすぎてしまった
- 逆に、厳しく指導すべき場面で甘くしてしまった
といった失敗を何度もしました。
また、特別支援の子たちの進路や未来についても曖昧な理解しかなく、最初は目の前の子どもたちの進学や将来を見据えた生活指導も意識ができていませんでした。
特別支援教育は「経験したことがあるかどうか」で大きな差が出ます。特別支援学級を経験するまで、私は障害児教育の専門的な知識がほとんどありませんでした。実際に担任してから、ようやく本や研修を通じて勉強し直したのです。
👉 ポイント:経験不足を補うには、研修参加や書籍から学ぶ習慣を持つことが重要です。私が最初に購入した本は以下の2冊です。
この2冊の本以外に、特別支援学級の担任として読んでよかったと思った本はこちらの記事で紹介しています
「特別支援教育を理解したい!特別支援学級の担任におすすめの本3選」
特別支援学級担任を経験して得られたこと
ここまで「しんどさ」を中心に書いてきましたが、特別支援学級担任には大きな学びもありました。
- 子どもたちの「小さな」成長を喜べるようになった
- 保護者対応の力がついた
- 将来を見通した広い観点で、教育を考える視点を持てた
特に「小さな成長を大切にする姿勢」は、通常学級に戻ったときにも役立ちました。
まとめ
特別支援学級は、決して「楽な学級」ではありません。
むしろ、子どもの成長が見えにくい・職場理解が得にくい・保護者対応が難しい・自分の知識不足に直面するといった、担任を悩ませる要素が多く存在します。
ただし、その経験を通じて得られる学びは大きく、教師としての力量を高める貴重な財産になります。
特別支援学級を担任する先生へ
「しんどい」と感じるのは自然なことです。でも、そのしんどさを乗り越えた先に、教師として大きな成長が待っています。今はレベル上げの真っ最中です。心と体を休めながら頑張ってください!
特別支援級以外の先生へ
特別支援級の担任の先生は、やってみないとわからない苦労や大変さがたくさんあります。
是非特別支援教育を学んでください。そしてご自分の学級経営力を高めるためにも、教員人生で一度は特別支援学級の担任にチャレンジしてみることをおすすめします。





コメント