【40代小学校教員の退職カウントダウン29:退職まで残り3年7ヶ月】
はじめに
教員の給料は実質減っていく。そう聞いてどう思いますか?
日本はインフレ時代に突入しました。インフレの時代、教員の給料の安定は裏目に出ます。下がる事もないけど、上がりもしないからです。
私は40代の小学校教務主任(担任兼務)
2028年度末に正規教員を退職する予定です。
【私が退職しようと決意した具体的経緯】
ここ数年、「物価が上がった」と実感している先生方も多いのではないでしょうか。
給食費、電気代、ガソリン代、そして日用品まで…。
日本は長らく「デフレ」でしたが、なぜ今インフレに転じたのか。
そして、この変化が教員の家計や資産運用の必要性にどう関わるのか。
今回は、インフレの背景を整理したうえで、教員が家計を守るために取るべき行動について考えていきます。
日本がインフレに転じた背景
- 円安の進行
アメリカが利上げ、日本は超低金利を維持。その金利差で円安が進み、輸入品が高騰。 - エネルギー・食料価格の高騰
ウクライナ危機やコロナ後の需要増で資源・食料の価格が世界的に上昇。 - 世界的なインフレの波及
欧米で10%近いインフレが起き、日本企業も値上げせざるを得ない状況に。 - 賃金上昇の兆し
世間では2023年以降、30年ぶりに大幅ベースアップが実現。物価と賃金が同時に動き出す可能性。教員の給料上昇が僅かなのに対し、初任給は30万円時代に突入しました。

👉 要するに、日本のインフレは「外部要因」で始まり、最近では「国内(賃金)」にも波及し始めているのです。
これから日本では、物価が上がるのが当たり前の時代に入ったと考えるべきでしょう。
インフレ構造はこれからの時代、必須の知識だと思います。もっと詳しくなりたい人はこの本がおすすめです。池上さんにわかりやすく教えてもらいましょう(笑)
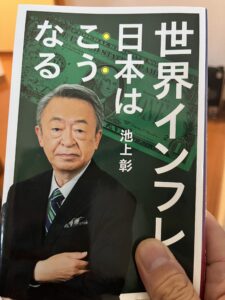
インフレが教員の生活に与えるリアルな影響
1. 食費のじわじわ上昇
- 食パン:120円 → 150円
- 冷凍うどん:30円台 → 50円台
- サラダ油:300円台 → 500円台
毎日のちょっとした値上げが、月数千円〜1万円以上の負担増に。
2. 光熱費の高騰
冬の暖房費や夏の冷房費が家計を直撃。
教員は長期休暇も自宅で過ごすことが多く、光熱費の上昇が特に響きやすいのが特徴です。
3. ガソリン代の上昇
- 2020年:130円台
- 2025年:170円前後
部活動や出張で車移動が多い先生は、月に数千円の負担増。
4. 実質給与の目減り
給与は「安定」していても、物価が3%上がれば年収600万円の教員は実質18万円分の購買力を失う計算に。
副業制限のある教員にとって、これは避けられないリスクです。

なぜ教員に資産運用が必要なのか
インフレの最大の特徴は「現金の価値が目減りする」ことです。
10年前に100万円で買えたモノが、今は120万円必要になる──これがインフレの現実。
安定収入が強みの教員ですが、給与水準は大きく上がらず、退職金や年金もインフレで実質的価値が削られる可能性があります。
だからこそ、資産を預金のまま眠らせず、インフレ率を上回る運用を目指す必要があるのです。
例えば、物価が年2%上がるなら、年5%成長する資産を持つことで実質的な購買力を守れます。
まとめ|インフレ時代の教員に必要な「家計防衛」と「資産運用」
日本がデフレからインフレに転じたのは、金融政策・円安・資源高・世界的インフレが重なった結果です。
教員にとっては、給与は安定しているのに実質的な価値が減っていくという新しい現実に直面しています。
だからこそ、
- 家計の見直し
- 支出の工夫
- インフレに負けない資産運用
この3つが欠かせません。
インフレ時代を賢く乗り切るために、教員こそ「安定」に頼らず、資産を守り育てる力をつけていきましょう。
このブログでは教員の資産運用について情報発信をしています。
ぜひ他の記事も読んでいってください!

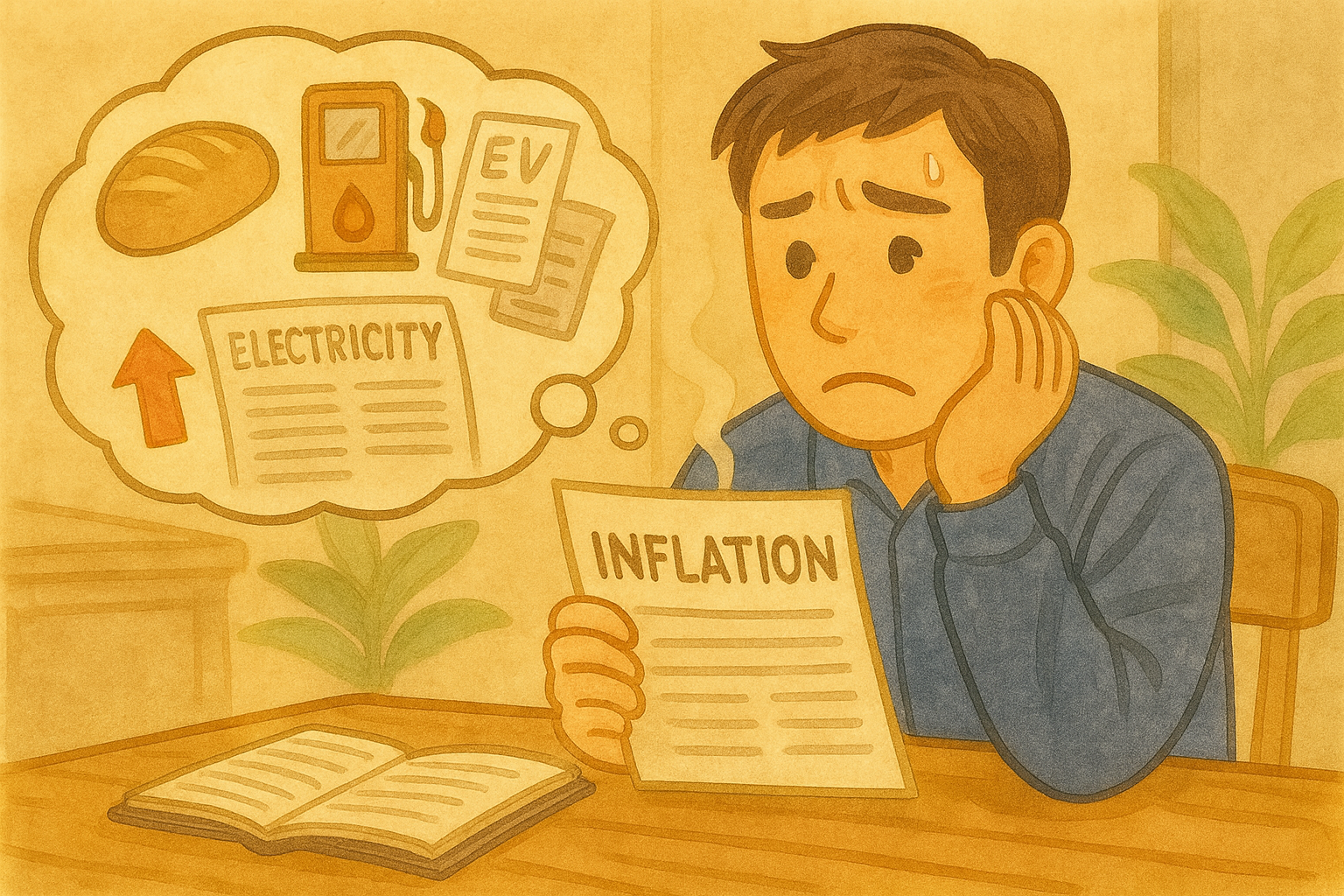


コメント