【40代教員の退職カウントダウン98:退職まで残り3年4ヶ月】
はじめに
私たち教員は、日々多忙ではありますが、給与や雇用の面では比較的安定した職業です。
私自身、教員になってから感じたのは、これまで「普通」だと思っていた自分の生まれ育った家庭が、実は経済的にも恵まれた“幸せより”の家庭だったということでした。
当たり前のように習い事に行き、記念日のプレゼントやケーキをもらい、子どもとして塾や学費などの心配をしたことがない。これが普通ではないという現実が教室には溢れています。
そして、世の中には想像以上に厳しい環境の中で生活している家庭や子どもたちが多く存在するという現実にも気づかされました。
そうした家庭を支える社会的な仕組みの一つが「生活保護」です。
しかし、この言葉に対しては、「働かない人のための制度」「税金の無駄遣い」といった誤解や偏見が根強く残っています。
SNSなどでは、いわゆる“生活保護バッシング”が定期的に起こりますが、実際の不正受給率は0.4%未満に過ぎません。
私は社会科の教員でもあります。
今回の記事では、教員の教養シリーズとして、「生活保護とはどんな仕組みなのか」「どんな人が対象なのか」「どんな課題があるのか」について、制度を正しく理解するための情報提供をしていきたいと思います。
この記事が、先生方の「クラスの子どもたちに対する理解の一助」につながれば幸いです。
私は40代の小学校教務主任(担任兼務)で、2028年度末に退職予定です。
詳しくはこちら→【私が退職しようと決意した具体的経緯】
生活保護とは——生存権に基づく制度
社会科的に言えば「生活保護」は、日本国憲法第25条に定められた「健康で文化的な最低限度の生活」を保障する制度です。
すべての人が人間らしく生きる権利を持つという「生存権」に基づいており、働けない・収入が途絶えたなどの事情があっても、生活を立て直せるよう国が支える仕組みです。
つまり、生活保護は「特別な人のための制度」ではなく、誰でも困ったときに頼ることができる“最後のセーフティネット”なのです。

お金を渡すだけではない——自立を支える制度
生活保護の目的は単なる金銭的援助ではなく、生活の自立支援です。
生活費を支給するだけでなく、医療・介護・就労など、個々の事情に合わせて支援が行われます。
主な扶助の種類
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 生活扶助 | 食費・光熱費・衣類などの日常生活費 |
| 住宅扶助 | 家賃や地代などの住居費 |
| 医療扶助 | 病院での診療費(現物給付) |
| 介護扶助 | 介護サービス利用料(現物給付) |
医療費や介護費は、国や自治体が医療機関に直接支払う「現物給付」です。
現物給付とは、医療機関の窓口で医療費を支払うのではなく、必要な医療サービスそのものを直接受けることができる仕組みのことです。
つまり、お金と支援サービスの両方で生活を支える制度と言えます。

誰が受けられる?——「世帯単位」での支援
生活保護は個人ではなく世帯単位で実施されます。
同居して生計をともにしている人を「世帯」とみなし、その全体の収入や資産を基準に審査が行われます。
支給額は「地域ごとの最低生活費」から「実際の収入」を引いた差額で決まります。
例えば東京都23区で50歳の単身者なら、生活扶助約7.7万円+住宅扶助約5.3万円=約13万円が目安です(地方では9〜10万円ほど)。
働いて得た収入には「勤労控除」があり、働く人が不利にならない仕組みもあります。つまり、「働く意欲を持つこと」が制度的にも支えられています。
現状と課題——「必要なのに届かない」
2022年3月時点で生活保護を受けている人は約204万人(約164万世帯)。
1990年代から3倍に増えましたが、実は必要としている人の2〜3割しか利用していないとされています。
利用が進まない主な理由
- 行政職員の不足や制度の複雑さ
- 「生活保護=恥」という社会的偏見
- 親族への扶養照会(「迷惑をかけたくない」心理)
とくに3つ目の「扶養照会」は申請のハードルになっています。
「扶養照会」とは、生活困窮者を親族が支援できないかを調べるものす。例えば幼い頃から折り合いが悪く成人後20年以上連絡をとっていない兄に照会連絡がいく、というようなパターンがあります。
2021年以降は申請者の希望で拒否できる運用になりましたが、民法上の扶養義務が残っているため、この問題が完全に解消されたわけではありません。
また、冒頭の生活保護バッシングにつながる話ですが、生活保護=恥の感覚が、本当に必要な家族が申請をすることに対する戸惑いにつながっています。
教育現場から見た生活保護
学校現場では、生活保護を受けている家庭や、生活保護に準じる経済状況の家庭も少なくありません。その支援として「就学援助制度」があります。
就学援助は、学用品費・給食費などを支給する仕組みで、教育の機会均等を守る制度です。
教員として、子どもの様子から家庭の変化を感じ取ることもあります。給食費の未納、文具がそろわない、家庭の会話の中に「お金がない」という言葉が出る——
そんなとき、制度を知っていれば、適切な相談機関へつなぐ判断ができるようになります。
生活保護を学ぶことは、福祉の専門家になるという意味ではなく、子どもの背景を理解し、支援の視点を持つという教師としての役割につながります。
生活保護バッシングの背景
生活保護に対する否定的な感情の多くは、
「自分は頑張っているのに、なぜあの人が支援を受けられるのか」という相対的不公平感から生まれます。
メディアで不正受給が報じられるたびに制度全体が批判されますが、実際には不正はごく一部であり、多くの受給者は真面目に生活を立て直そうとしています。
全体で見れば一部の受給者が不正を働いたり、制度の上であぐらをかいているのです。
社会科の授業でも、「福祉=税金で支える制度」ではなく、「みんなで支え合う仕組み」としてとらえ直すようにしたいと考えています。
生活保護を学ぶことは、福祉教育の入り口としても意味があります。
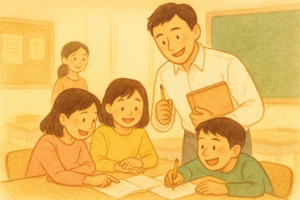
これからの生活保護——支え合う社会に向けて
戦後の制度をそのまま引き継いでいる生活保護法は、高齢化や非正規雇用の増加、単身化が進む現代に完全には対応できていません。
今後は、デジタル申請やオンライン相談の拡充など、より利用しやすい制度設計が求められています。
「恥の制度」ではなく、「支え合いの制度」へ。その転換が社会全体の課題だと思っています。そのために我々教師は生活保護に対して正しい知識を持つべきだと思います。
おわりに
生活保護を学ぶことは、単に制度を知ることではなく、社会の仕組みを理解することにつながります。
私たち教員は、経済的に恵まれた立場にいるからこそ、困難な状況にある家庭の支援策を知り、必要なときに動ける存在でありたいと思います。
教育と福祉は切り離せません。今回の記事が、教員としての「社会を知る教養」を深める一助になれば幸いです。

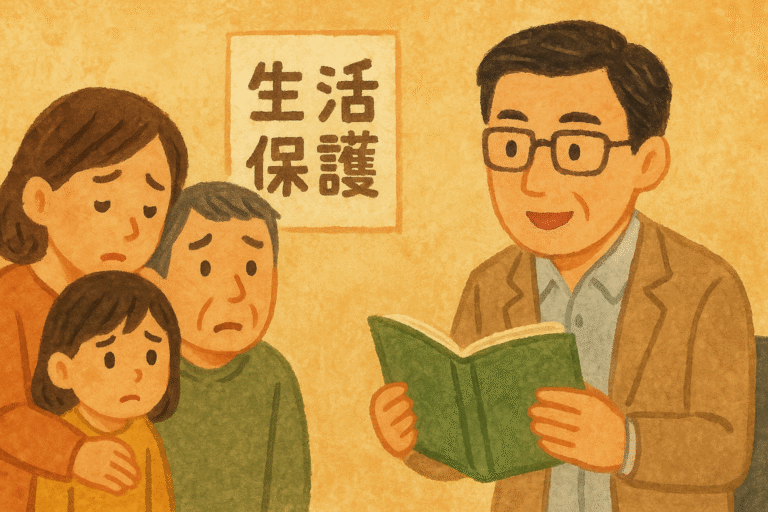


コメント