【40代教員の退職カウントダウン93:退職まで残り3年4ヶ月】
はじめに
夏休み、部活動の大会役員として中学生のバスケットボール大会に参加したとき、5年ぶりにかつての指導者仲間に再会しました。
彼は私より8歳年下ですが、県内でも有名な強豪チームを率いる名将の一人。何度も対戦を重ねた、まさに“良きライバル”であり“戦友”のような存在です。
そんな彼が昨年、教員を辞めたと聞いたときは正直驚きました。
なんと、これまでの部活動指導で培った経験と実績を生かし、バスケットボールのクラブチーム運営で生計を立てるという新しい挑戦を始めていたのです。

私と顔を合わせていなかった間の5年の間に、彼にどんな転機があったのか。先日改めてお酒を交わしながら彼のチャレンジの話を聞いてきました。
今回はその時聞いた話をベースにHOW TO 教員の転職シリーズとして彼の挑戦を皆さんに共有したいと思います。
私は40代の小学校教務主任(担任兼務)。2028年度末に正規教員を退職予定です。
詳しくはこちら→【私が退職しようと決意した具体的経緯】
人生の転機を意識する同世代の先生方にとって、今回の記事が「教員を辞めたその先」を考える一つのきっかけになれば幸いです。
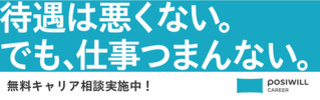
バスケットボール界で鳴り響く美術教師の名声
彼は現在36歳。一昨年までは中学校の美術教師でした。
新任当初からバスケットボール部の顧問を任されましたが、実は競技経験はゼロ。サッカー経験者で、バスケットボールは「観るのが好き」なだけだったそうです。
ところが、1年目の夏の大会で初戦敗退を経験したことが、彼の指導者人生を大きく変えました。
持ち前の負けず嫌いな性格から、部活動指導にのめり込み、わずか2年目で市内大会優勝、3年目には全県大会へ出場を果たします。
彼の戦術は、サッカー出身ならではの発想で、既存のバスケットボールの常識にとらわれないものでした。その独自性と柔軟さには、何度も驚かされたものです。
また、彼は非常に勉強熱心で、県外の有名指導者のもとへチームを連れて指導法を学ぶなど、研鑽を惜しみませんでした。
その結果、3年目以降は全県大会の常連校として名を馳せるようになります。
私は近隣自治体の学校で顧問をしていましたが、すぐに彼の名前は耳に入ってきました。
その後、練習試合を申し込むなどして交流が始まり、互いに指導法を語り合う仲になりました。
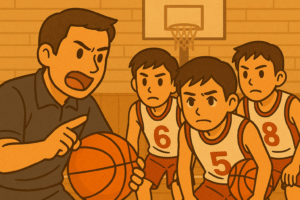
どんどんやりにくくなる部活動
誤解のないように最初に伝えておきますが、私はかつて部活動指導に情熱を注いできた「部活教師」でした。しかし今は、部活動はできるだけ早く廃止すべきだと考えています。
この点については、以前の記事で詳しくまとめています。
→【部活動を考えてみる ― 教員不足と「部活大好き教員(BDK)」の視点から】
→【それでもやっぱり部活動は廃止すべき理由 ― BDK(部活大好き教員)が語る本音】
彼が勤めていた自治体は、全国的にも比較的先進的に地域移行を進めていました。
特にコロナ禍以降、部活動縮小の流れは加速します。それに加えて、体罰や暴言などのセンシティブな問題への対応も求められるようになり、彼自身、「部活動の顧問が年々やりにくくなっている」と感じていたそうです。
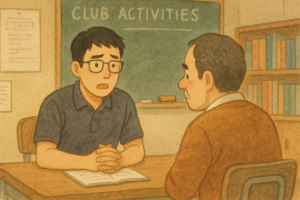
一方で、彼のもとには近隣の中学校の子どもたちから「指導を受けたい」という依頼が相次ぎました。そのため、社会体育の立場でバスケットボールクリニックを何度も開催。
参加費を徴収してはいましたが、教員の副業は原則禁止のため、実際に手元に残るのは体育館の使用料程度。それでも、彼は子どもたちのために指導を続けました。
まさに、「教員」という枠を超えて、純粋にスポーツ教育の在り方を追求し始めた時期だったのです。

スポーツ指導を「個人事業」にするという選択
教員という仕事に限界を感じていた彼にとって、唯一、心から情熱を注げるのが部活動指導でした。
そこで彼は、「スポーツ指導で生計を立てることはできないか」と真剣に考え始めます。
彼の計画は、非常に現実的で明確なものでした。
もし自らクラブチームを立ち上げれば、すでに指導を受けたいと希望していた生徒が30人以上は集まる見込みがありました。さらに、中学校クラブチームにつながるミニバスケットボールチームを同時に設立すれば、合わせて50人以上のクラブ員が見込めます。
月謝を1人あたり5,000円と設定すれば、月収は約25万円。
そこに、美術教師としてのスキルを生かし、チームTシャツやバッグ、ユニフォーム、チームタオルなどのオリジナルデザイン商品を製作・販売して収益を上乗せします。
遠征費用などは別途徴収し、運営コストを賄う仕組みです。
さらに、子どもたちが学校に通う平日昼間は、アルバイトなどの副業を行うことで収入を補う。独身の彼にとっては、十分に生活可能な見通しが立ちました。
こうして彼は2023年度末、ついに教員を退職。
退職金の一部でデジタルタイマーなどの備品を購入し、念願の個人事業主としてのスポーツ指導をスタートさせました。

教員を辞めて見えた現実と課題
クラブチームの立ち上げから数ヶ月。彼の挑戦は順調に見えましたが、現実は甘くありませんでした。
子どもたちの笑顔に囲まれながら指導する時間は確かに充実していました。
しかし、教員時代にはなかった経営のプレッシャーがのしかかってきたのです。
たとえば、体育館の確保。学校施設の利用には自治体との調整が必要で、思うように使えないことも多い。
また、月謝の集金や会計処理、保護者対応、SNS運営など、「指導以外の仕事」が膨大にあることに気づかされました。
さらに、部活動と違って「退会」も現実的なリスクです。家庭の事情や進学によって生徒が離れると、そのまま収入減につながります。
まさに「教育」と「ビジネス」の狭間で揺れる葛藤でした。
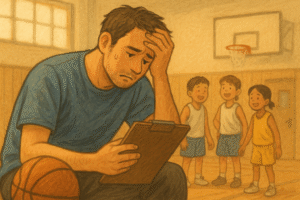
それでも彼は、「教員時代よりも自由に、自分の信じる指導ができる」と語ります。
チームのコンセプトは「チームとして勝つこと」ではなく、「個人の力を徹底的に伸ばすこと」だそうです。
つまり、目指すのは大会での優勝ではなく、ひとり一人のスキルアップ。ドリブル、1on1、フィニッシュ、判断力といった個人技をとことん鍛え、その成果をそれぞれが所属する学校の部活動で発揮してもらう。結果として、レギュラー獲得や高校進学での推薦につながる――という考え方です。
いわば「バスケットボール版の学習塾」。
部活動や地域のクラブチームのように“みんなで強くなる場所”ではなく、“あなた自身を強くする場所”として設計されているのが特徴です。
これは、これまでの「学校部活動」や「社会体育クラブ」とは明らかにニーズが違います。 従来型の部活動がカバーしきれない部分――技術的な個別指導、高校進学も見据えた育成、保護者の“成果が目に見える安心感”――に応える経営戦略だと言えます。
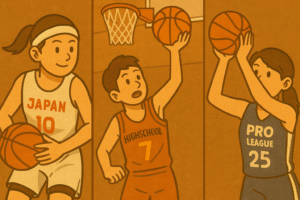
まとめ ― “情熱”を仕事に変えた元教師の挑戦
現在、彼のクラブチームには小中学生あわせて70人以上が在籍しています。
個人事業としてのスタートは順調で、当初予定していた午前中の副業も行わず、今はチーム運営に全力を注いでいるそうです。
もちろん、このチャレンジは誰にでも真似できるものではありません。
彼にはもともとあった指導者としての名声、独身で身軽な家庭状況、スポーツへの情熱、そして美術教師としてのデザインセンスという強みがありました。
それらがうまく組み合わさった、非常に特殊なケースと言えるでしょう。とはいえ、「自分の強みを活かして生計を立てる」という点では、彼の姿は多くの教員にとってのロールモデルになるはずです。
学校という枠を越えて、教育的情熱を“仕事”に変えた好例とも言えるでしょう。
彼の挑戦は、まだ始まったばかりです。
これからも一人の友人として、そして同じ教育に携わる者として、彼の歩みを見守っていきたいと思います。
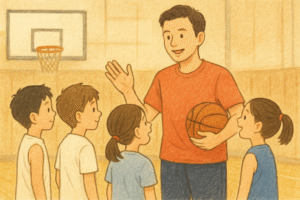
合わせて読みたい:HOW TO 教員の転職シリーズ
【HOW TO 教員の転職シリーズ|8つの実例とキャリア戦略で“これからの働き方”が見えてくる】
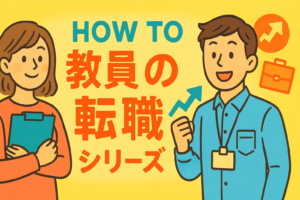

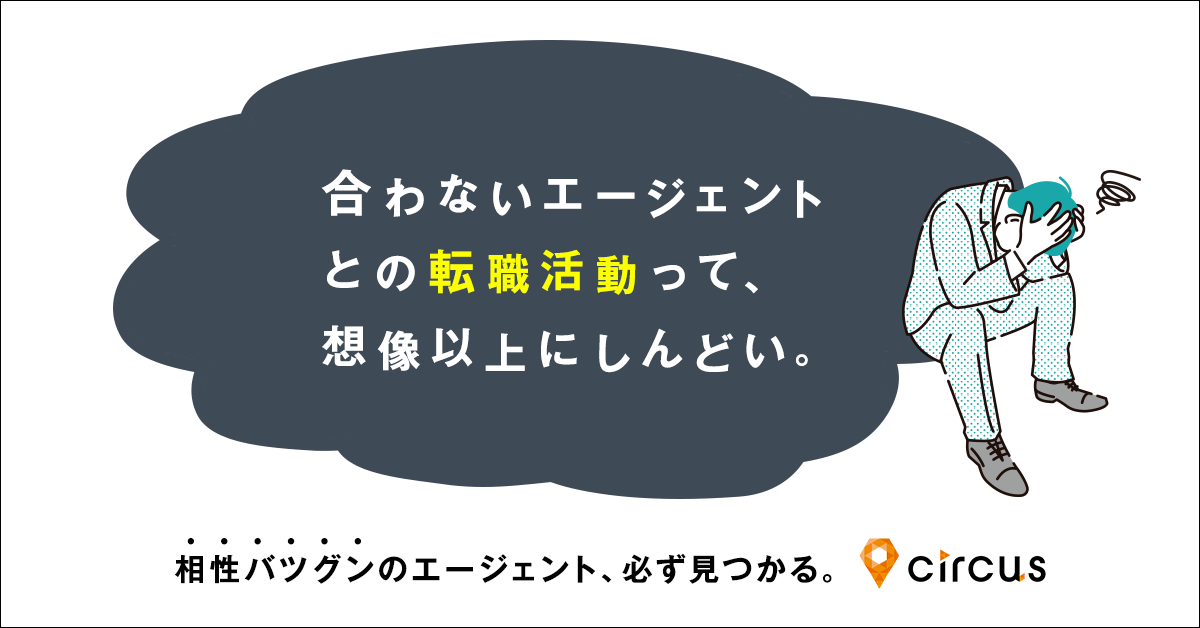

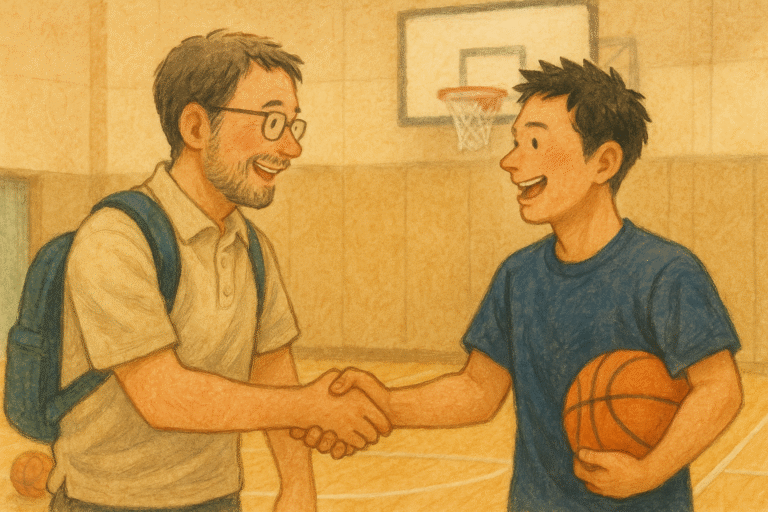
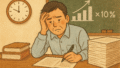
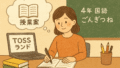
コメント