【40代教員の退職カウントダウン87:退職まで残り3年5ヶ月】
はじめに
「やっと休日なのに、なぜか気持ちが落ち着かない」
「1日寝ても、疲れが抜けない」
「休みのはずなのに、学校のことが頭から離れない」
多くの先生が、こんな“休日のしんどさ”を感じています。
平日はもちろん多忙。やっと訪れた休みなのに、リラックスできない。
その結果、「休んでも疲れが取れない」という悪循環に陥ってしまう。そんな精神状態に心当たりはありませんか?
私は40代小学校教務主任(担任兼務)、2028年度末に正規教員を退職予定です。
詳しくはこの記事をどうぞ→【私が退職しようと決意した具体的経緯】
教員の「休日がつらい」現象とは
この現象は、一般的な“疲労”とは少し違います。
体を休めても、心が休まらない。それは、「常に気を張り続ける仕事」である教員ならではの特徴です。
- 休日でも、ふと授業の準備や子どもの顔を思い出してしまう
- 学年だより、成績処理、報告書……「終わっていない仕事」が頭に浮かぶ
- 休みの日にもLINEや業務チャットが入る
- 「休み明けの月曜」が怖い
気づけば、「仕事から離れている時間」が休みの日であってもほとんどない。
これが、教員特有の“休んでも休まらない状態”を生み出しています。
この状態は「寝れば元気になる」ではないのが厄介なところです。
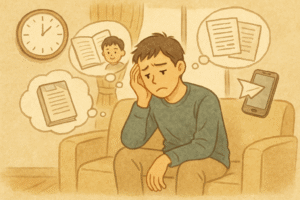
私の妻が教員を辞めた一番の理由が、この「土日や夏休みで、完全に頭の中から仕事が消えた時なんてあっただろうか?常に脳のリソースの一部が仕事に取られている!」状態です。
妻は転職して改めて「やっぱり教員をやっていた時は、本当の意味での休日はなかった。ゆっくりできる休日がある、それだけで転職した価値があった!」と言っています。
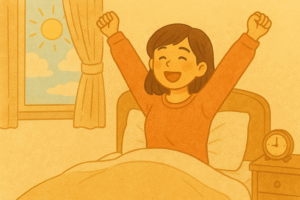
私が教員を辞めようと思った経緯や、妻の転職の経緯はこちら↓
【私が退職しようと決意した具体的経緯】
なぜ休んでも疲れが取れないのか
① 「オン」と「オフ」の切り替えができない
教員の仕事は、「授業」「行事」「保護者対応」「部活動」など多岐にわたります。
しかもそれが“人”を相手にした仕事であるため、責任感や感情のエネルギーを常に使います。
平日はフルスロットルで動き、休日になっても頭が止まらない――。
まるでエンジンを切らずにアイドリングしている状態です。

② 「やらなきゃ」が休みを侵食してくる
教師の休日は、表向きは“休み”でも、実際にはこうです。
- テストの採点や学級通信を持ち帰っている
- 家にいても、次の授業のことを考えている
- 行事前は休日も準備に出勤
- 部活動のために出勤しなければならない
つまり、「休みの日=仕事が遅れを取り戻す日」になっている。これでは、休むどころか「追われる休日」です。
③ 「休むこと」に罪悪感を抱いてしまう
「自分だけ休んで申し訳ない」「他の先生も頑張ってるから、休んでいられない」
そんな気持ちが心の中で休むことを邪魔します。
これは、真面目で責任感の強い先生ほど陥りやすい考え方です。
でも、心が休まらない休日は、長期的に見れば仕事のパフォーマンスを下げる結果になります。

教務主任として感じる現実
教員の働き方を見ていて感じるのは、「多くの先生が“仕事以外の自分”を持てなくなっている」ということです。
休日が「ただ寝る日」や「明日に備える日」になってしまう。でも、それでは人としての“回復”が起きないと思います。
私は教務主任として、こう考えています。
休むことは、仕事の一部。むしろ「きちんと休む力」がある先生ほど、長く良い仕事を続けられる。
だから、休日に心から休めない先生を見ると、本気で心配になります。
責任感のある先生ほど、限界まで頑張ってしまうからです。何より昔の私がそうでした。
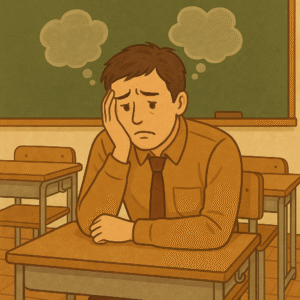
「休日がつらい」を抜け出す3つのヒント
① 休日の“予定”をあえて入れる
「何も予定を入れずに休もう」と思うと、結局仕事のことを考えてしまいがちです。
思い切って、好きなカフェに行く・映画を見る・散歩するなど、
“自分のための予定”を最初に入れておきましょう。
疲れているのに予定なんて、と思うかもしれませんが、私の経験上寝ることよりも心のスイッチをOFFにする方がよっぽど回復します。「今日はこれをする」と決めておくことで、心のスイッチが切り替わりやすくなります。
私は自分の心をOFFにするためにサウナを活用しています。頭を空っぽにできるサウナが私にとっての至福の時間です。
[サウナで整う!ストレス社会に挑む教員のリセット法]

② “回復のリズム”を見つける
休み方にも、人それぞれ合うスタイルがあります。
- 午前は家事や外出、午後は完全オフ
- 1日家でゆっくり、夕方だけ外出
- 朝だけ学校関係のことをして、午後はリセット
自分に合った“休息リズム”をパターン化しておくと、休日の不安が減ります。
③ 「休む=チームへの貢献」と捉える
教務主任として伝えたいのは、休むことはチームプレーの一部であるとマインドチェンジして欲しいということです。
先生が疲れ切っていると、授業にも職員室にもその雰囲気が伝わります。
あなたがしっかり休むことで、子どもにも他の職員にも“安心感”が生まれます。
「休むことはわがまま」ではありません。元気に戻ってくることが、職員室への最大の貢献です。
合わせて読んで欲しい:教員の健康を考えるシリーズ
【教員の健康を考えるシリーズまとめ|休憩・食・睡眠・姿勢・ストレスケアで整える働き方】

おわりに
「休みなのに、休まらない」
――それは、心がSOSを出しているサインかもしれません。
休日に罪悪感を抱くほど、あなたはきっと真面目で、責任感のある先生です。
でも、心と体を守ることは、先生の仕事の一部です。
子どもたちに「無理しないでね」と言うように、自分にも「しっかり休もう」と優しく声をかけてください。
休むことは、逃げることではない。
立ち止まって、自分を取り戻すための“前進”です。
どうか安心して、あなたの休日を「心のメンテナンスの日」にしてください。

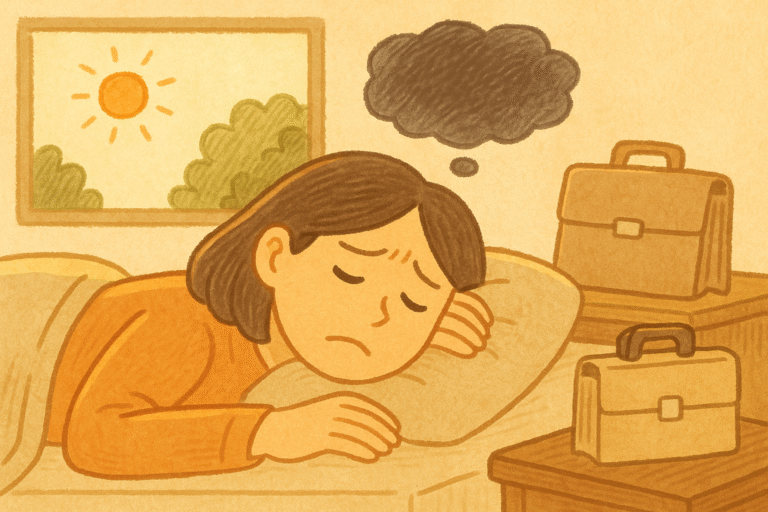


コメント