【40代教員の退職カウントダウン91:退職まで残り3年4ヶ月】
はじめに
「体調が悪くても、授業があるから休めない」「自分が休んだら、子どもや同僚に迷惑をかけてしまう」
そんなふうに思って、無理をして出勤してしまう――。
先生たちの中には、ギリギリまで頑張ってしまう人が少なくありません。でも本当に、「休まないこと」がいい先生の条件なのでしょうか。
先日、長く付き合いのある後輩から「しばらく休むことになりました」という連絡をもらいました。軽度ではあるものの鬱だと聞きました。
彼は小学校で6年間勤務したあと、中学校に転勤して2年目。力のある若手で、周囲からの信頼も厚い先生でした。しかし、責任感が強く「期待に応えたい」という気持ちが先行してしまい、無理を重ねていたようです。
職場が違うとはいえ、彼の力になってあげられなかったことが心残りです。
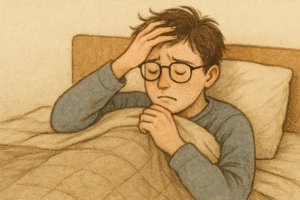
20年以上学校にいると、彼に限らず“無理をし続けた結果、長期休養が必要になった先生”を何人も見てきました。教務主任として伝えたいのは「短期間休むことは、まったく問題ではない」ということです。
むしろ、無理をして働き続けた結果、長期で休まざるを得なくなるほうが、学校にとっても子どもたちにとっても、そして何よりも自分自身にとって大きなダメージになります。
今回の記事は、彼の力になれなかった私自身の反省も込めて、いま無理をしている先生に少しでも届けばと思い、今の気持ちを綴りました。
私は40代小学校教務主任(担任兼務)、2028年度末に正規教員を退職予定です。
詳しくはこの記事をどうぞ→【私が退職しようと決意した具体的経緯】
なぜ先生は「休めない」と感じるのか
多くの先生が「休めない」と感じるのには、いくつかの理由があります。
- 「授業があるから代わりがいない」
担任を持っていると、「自分しかできない」と思い込みがちです。
子どもたちへの責任感が強い先生ほど、授業を任せることに抵抗を感じやすいものです。 - 「他の先生に迷惑をかけたくない」
職員室では、周りの先生が忙しく動いている姿を日々目にします。
そんな中で、「自分だけ休むのは申し訳ない」と感じてしまうのは自然なことです。 - 「自分が抜けると学校が回らない」
責任感が強い先生ほど、この思い込みを抱えがちです。
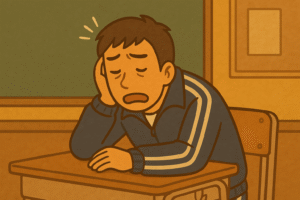
けれども、学校はチームで動く場所。誰かが抜けても、他の誰かが『一時的には』カバーできます。わかってほしいのは――
あなたの「1日」は、誰かが代わりに担うことができる。しかし、あなたの「1ヶ月」をかわることは非常に難しいということです。
だからこそ、“無理をする前に休む”ことが、子どもや同僚、そして自分を守る一番の方法なのです。

教務主任として感じること
私はこれまで、若い先生もベテランの先生も、無理をして限界まで働き続ける姿を何度も見てきました。
「責任感が強いからこそ、休めない」――でも、その責任感が、自分を追い詰めてしまうこともあります。
だからこそ、こう伝えたいのです。
辛いときは休めば良い。ズル休みだっていいから仕事を忘れてリフレッシュして欲しい。
以前書いたブログでも告白していますが、私も若い頃ズル休みをしていました。もちろん罪悪感はありましたが、その「ズル」によって私自身の心の健康を保つことができたと思っています。
【教員が倒れる理由は“忙しさ”ではない。― メンタルをすり減らす本当の原因】
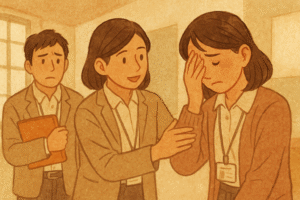
「今日は無理です」と言えることが、チームにとって一番の誠実さです。助け合って離脱しないこと、それこそが本当の責任です。
1日休む勇気を持てる先生の方が、結果的に長く現場に立ち続けています。
私たち教務主任や管理職の仕事は、そうした「働き続けられる仕組み」をつくることでもあります。
罪悪感を減らす3つの考え方
① 「休む=自己管理の一部」と考える
体調を崩すのは怠けではありません。
休むこともまた、「次の日に向けての準備」です。
学校は先生の健康あってこそ成り立ちます。休むことは「迷惑」ではなく、仕事の一部と捉えてください。
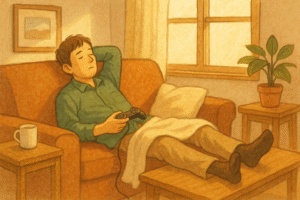
② 「代わりができる仕組み」を日常で整える
急な欠勤の不安は、「自分しか知らないこと」が多いことから生まれます。
日ごろから次のような工夫をしておくと、安心して休めます。
- 学級日誌や連絡帳に情報を残しておく
- 教材やプリントを共有フォルダに保存
- 子どもたちに「誰が教えてもできる活動スタイル」をつくる
これは“休む準備”ではなく、“チームで支える準備”です。
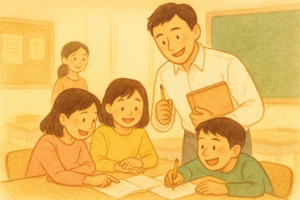
③ 「自分が休むことで、職場が優しくなる」
「自分が休むなんて申し訳ない」と思うかもしれません。
でも、あなたが勇気を出して休むことは、周りの先生が休みやすくなる第一歩です。
「○○先生も無理せず休んでいいんだ」と思える職場は、結局のところ、長く続けられるチームになります。
休むときに伝える言葉はシンプルでいい
体調不良で休むとき、つい気を使って言葉を選びすぎてしまうものです。
けれども、短く・簡潔に伝えるだけで十分です。たとえば、次のような言葉で問題ありません。
- 「体調が悪く、今日は休ませてください。」
- 「無理をすると長引きそうなので、お休みをいただきます。」
言い訳を探したり、状況を細かく説明したりする必要はありません。
淡々と伝えるだけで大丈夫です。
そもそも年次有給休暇(年休)は、法律で保障された労働者の権利です。
以下のポイントを知っておくと、安心して休むことができます。
🌿 年休取得の基本ポイント
- 取得の原則: 年休は労働者の権利であり、学校(雇用者)が理由を問わず拒否することはできません。
- 休みの理由: 体調不良や私用など、理由を説明する義務はありません。
※ただし、職場運営上の連絡として簡潔に伝えるのはマナーです。 - 時季指定義務: 使用者(自治体・学校)は、10日以上の年休が付与された職員に対して、年5日間の取得させることを義務づけられています(労働基準法第39条)。
「迷惑をかけたくない」気持ちは大切ですが、休むことも立派な仕事の一部だと思いましょう。

「離脱しないこと」が最大の責任
学校の仕事はチームプレーです。
一人が全力で走り続けるよりも、全員が長く立ち続ける方がはるかに強い。
「今日1日を休む」ことは、「明日も子どもたちの前に立ち続けるための選択」です。
どうか、休むことを恐れないでください。休む勇気は、先生としての覚悟の証です。
合わせて読んで欲しい:教員の健康を考えるシリーズ
【教員の健康を考えるシリーズまとめ|休憩・食・睡眠・姿勢・ストレスケアで整える働き方】

おわりに
教員という仕事は、「人を育てる」という尊い使命を背負っています。
けれど、その使命感が強すぎると、気づかないうちに自分を追い込んでしまう。
私は教務主任として、「先生たちが離脱せずに、笑顔で続けられる職場」をつくりたいと願っています。
もしあなたが今、疲れを感じているなら、どうか思い出してください。あなたの健康は、学校にとっても大切な資源です。
だから、安心して休んでください。それが、いちばんの責任の果たし方です。
冒頭の後輩が1日でも早く元気になってくれることを祈っています。

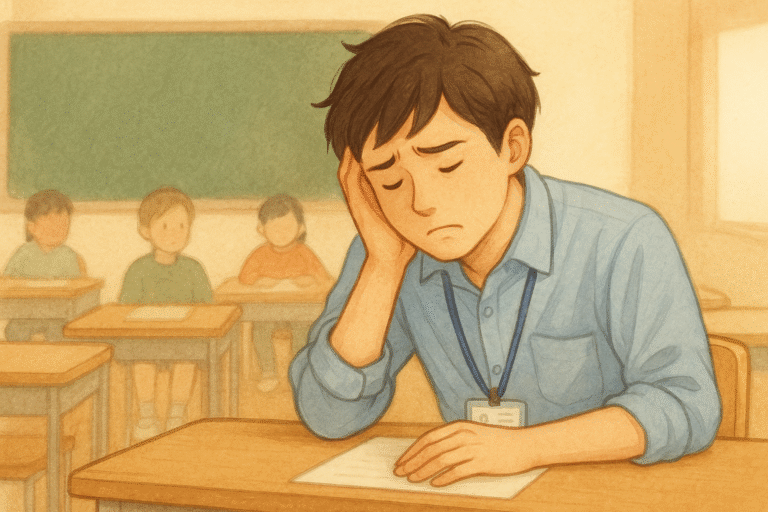

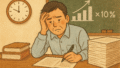
コメント