【40代教員の退職カウントダウン86:退職まで残り3年5ヶ月】
はじめに
2009年から始まった「教員免許更新制度」。廃止されて数年が経ちます。
当時は報道等で「これで教師の質が上がる」と言われましたが、現場の反応は必ずしも歓迎一色ではありませんでした。
私も現職教員としてこの制度のもとで働いてきた一人です。素直な感想として「この制度は本当に我々のためになっているの?」と疑問を感じることが少なくありませんでした。
そして2022年、この制度は廃止されました。なぜ生まれ、どんな成果を残し、そしてなぜ終わったのか。
一人の教師としての実感も交えながら、振り返ってみたいと思います。
私は40代小学校教務主任(担任兼務)、2028年度末に正規教員を退職予定です。
詳しくはこの記事をどうぞ→【私が退職しようと決意した具体的経緯】
合わせて読みたい:教員の教養シリーズ『教員免許』
【HOW TO 教員免許の取り方 〜教員免許が取得できる6つのルートを徹底比較〜】
【教員資格認定試験とは?社会人でも教員免許が取れる“もうひとつの道”を徹底解説】
【教員免許更新制度はなぜ廃止されたのか?制度が生まれた理由と、現場が感じた限界】
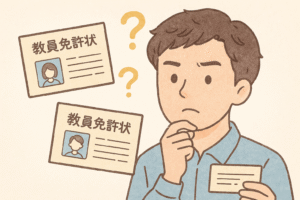
教員免許更新制度とは
「教員免許更新制度」とは、すべての教員が10年ごとに講習を受け、免許を更新しなければならないという仕組みです。
目的は「教員として必要な資質・能力の維持向上」。講習は大学などが開設し、約30時間の受講が必要。
費用や交通費は基本的に教員の自己負担。
多忙な中、夏休みを削って講習を受ける先生も多くいました。
制度としては、「常に新しい教育内容を学び続ける教員」を目指したものでした。
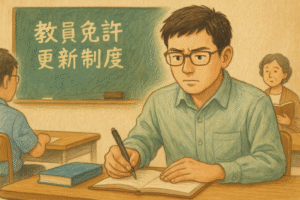
制度ができた理由
では、なぜこんな制度が作られたのでしょうか。
背景には2000年代の「教育改革」の流れがありました。
いじめや学力格差が社会問題になり、「教員の資質を高める仕組みが必要だ」という声が高まっていたのです。また、「不適格教員を排除するための制度ではないか」という指摘もありました。
当時はマスコミでも「質の低下」「教師失格」などの言葉がよく取り上げられ、教師への視線は厳しい時期でした。
その中で「免許に有効期限を設け、定期的に講習を受けさせよう」という方針が打ち出され、2007年に法改正。2009年に施行されました。安倍内閣の時です。
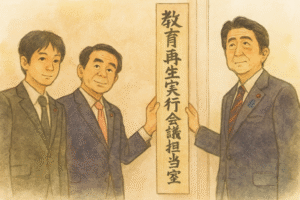
【安倍政権の教育改革を振り返る──理念・成果・課題を中立的に整理する】
【教育基本法の改正って何だったの?──若手の先生にわかりやすく解説】
制度がもたらしたもの
私自身、更新講習を受けた経験があります。
大学の大講義室で、何十人もの教員が一斉に受ける講義。メインは「2020年からスタートする新学習指導要領について」の講義でした。
テーマはICT活用やいじめ防止、特別支援教育など、テーマは時代に合わせて更新され、確かに、最新の教育理論や事例に触れられる場ではありました。
ふだん出会えない他校の先生と話す機会もあり、「刺激になった」と感じたことも覚えています。
一方で、正直に言えば「現場で活かせる内容は少なかった」というのが本音です。
講習を主催する大学側に「教員の資質を高めよう」という強い意志がなく、制度なのだからとりあえずやっておこう感が強かったように思います。
30時間をかけても、翌日の授業が劇的に変わるわけではない。
むしろ、
「夏休みがまた講習で埋まる」「自腹で交通費を払って受ける意味があるのか」
そんな声が職員室でも多く聞かれました。
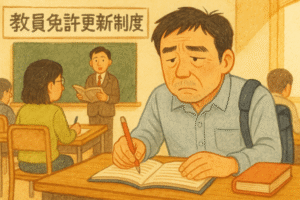
なぜ廃止されたのか
制度の廃止が決まったのは2022年。導入からわずか13年での幕引きでした。
理由はいくつもあります。
- 教員の負担が大きすぎたこと。
- 効果が見えにくく、実践的でなかったこと。
- 手続きの煩雑さによる「うっかり失効」問題。
- 教員志望者の減少に拍車をかける懸念。
特に「現場の負担感」は大きく、文部科学省が行った調査でも、多くの教員が制度に否定的でした。私自身も、忙しい学期末に「講習の申込期間」を確認する余裕がなく、管理職に指摘されてヒヤッとしました。
全国的にも「免許失効で教壇に立てなくなった」というケースが実際に起きました。
制度の理念は理解できるものの、現場の実情と合っていなかったのです。
廃止後の新しい仕組み
更新制がなくなっても、「学び続ける教員」という方針そのものは変わっていません。
2022年以降は、「任命権者による研修制度」に引き継がれました。
つまり、各自治体や教育委員会が、教員一人ひとりの研修履歴を記録・支援していく形です。
国が一律に「30時間の講習を受けろ」と命じるのではなく、現場の実情に合わせた柔軟な研修を行う方向へとシフトしました。
たとえば、
- 若手は授業づくり中心
- ベテランはマネジメントや特別支援教育 といった具合に、個々の課題に応じた学びを促す仕組みです。
制度の形は変わっても、「学び続ける教員」をどう支えるか——。そこが、これからの教育行政に問われている部分だと思います。
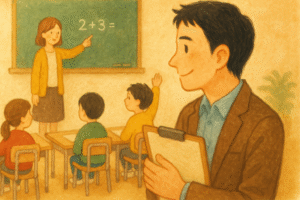
これからの教員に求められるもの
更新制が終わっても、教員の学びが終わったわけではありません。
むしろ、「制度に頼らず、主体的に学ぶ時代」に変わったといえます。AI教育、特別支援、外国籍児童、オンライン授業…。
現場の変化は早く、教員自身がアップデートを怠れば、すぐに取り残されます。
ただし、それは「自己責任」という意味ではありません。
教員が安心して学び続けられるよう、時間的・制度的な支援を整えることこそ、次の課題です。
制度を廃止して終わりではなく、「どう支えるか」を考える段階に来ている。そう感じます。
おわりに
教員免許更新制度は、「教員の質を高めたい」という善意から生まれた制度でした。
しかし、現場の実情や働き方を無視した仕組みでは、理想は実現できなかった。
制度が終わった今こそ、私たち一人ひとりが
「どんな学びを続けたいか」「どんな教師でありたいか」
を改めて考える時期なのかもしれません。

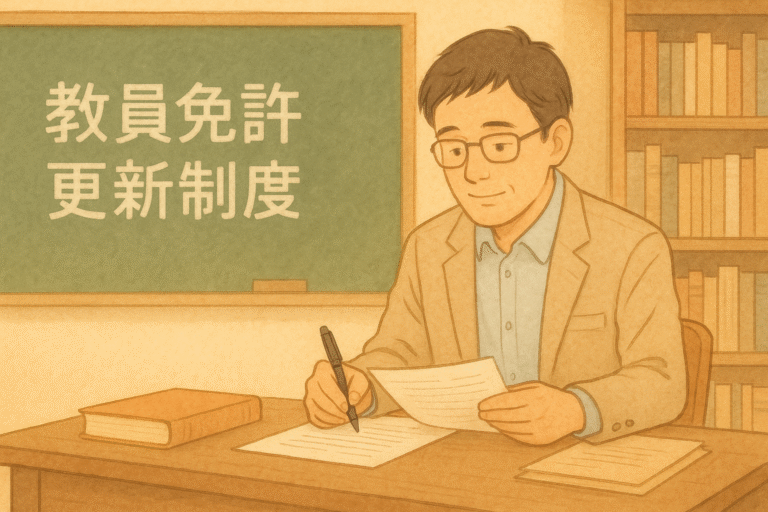
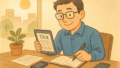

コメント