【40代教員の退職カウントダウン70:退職まで残り3年5ヶ月】
はじめに
教員同士で結婚するケースは少なくありません。安定した収入、長期的な勤務見込み、そして共働き——。
これらの条件から、「教員夫婦でペアローンを組んでマイホームを買う」という選択をする先生方が増えています。
しかし、住宅ローンの審査に通りやすい教員夫婦ほど、「借りすぎのワナ」に陥ることがあります。
この記事では、ペアローンの基本を踏まえたうえで、教員夫婦が注意すべき5つのデメリットを具体的に整理します。
私は40代小学校教務主任(担任兼務)、2028年度末に正規教員を退職する予定です。
詳しくはこちらの記事から→【私が退職しようと決意した具体的経緯】
家計の見直しシリーズで住宅購入について考えた記事はこちら↓
「固定費見直しシリーズ④ ― 住居費を整えると家計は一気に軽くなる」
「教員は持ち家がいい?——住宅ローンの“借りやすさ”が生むメリットと落とし穴」
ペアローンとは?
ペアローンとは、夫婦それぞれが1本ずつ住宅ローンを契約する仕組みのことです。
たとえば5,000万円の家を購入する場合、夫が3,000万円、妻が2,000万円のローンをそれぞれ組む——このような形になります。
一見すると「共働きなら効率的」と思える制度ですが、長期的に見るとリスクも多いです。
ペアローンのメリット・デメリットをそれぞれ確認してみましょう
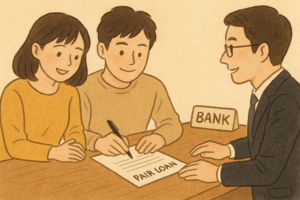
「ペアローン」のメリット5選
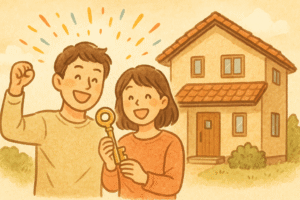
1. 借入額を増やせる
単独では届かない価格帯の物件にも手が届く、あるいは頭金を抑えられます。
実際、若年層では単独ローンよりペアローンのほうが中央値で借入額が大きい傾向にあります。
ただし、これは同時にデメリットの裏返しでもあります。
教員はローン審査において「安定した職業」として高く評価されやすく、銀行から提示される借入上限額が高くなりがちです。
そこにペアローンを組み合わせると、さらに上限額が引き上げられます。
そのため、「借りられる金額」ではなく「無理なく返せる金額」を基準に判断する経済感覚が欠かせません。
2. 借入条件を柔軟に設定できる
ペアローンは夫婦それぞれが1本ずつ契約するため、金利タイプ(固定・変動)や返済期間を分けて設定できます。
たとえば、夫は短期・変動、妻は長期・固定といった組み合わせが可能です。ライフプランに合わせた設計力がカギになります。
3. 夫婦2人とも団信に加入できる
それぞれが団体信用生命保険(団信)に加入でき、万一の場合、その人のローン残高は0円になります(商品による)。
収入合算のローンだと契約者しか団信に入れないため、ここは大きな安心材料です。
4. 住宅ローン控除が2人分使える
条件を満たせば、夫婦それぞれで住宅ローン控除が適用されます。
負担している税額の範囲内で節税効果が広がり、単独ローンよりお得になるケースもあります。
※連帯債務型の収入合算でも適用される場合あり。
5. 売却益の「3,000万円特別控除」が2人分
将来マイホームを売却して利益が出た場合、最大6,000万円(夫婦各3,000万円)まで非課税となるケースがあります。
資産性の高い家を選べば、この優遇を活かして大きな節税につながります。
教員夫婦が注意すべきペアローンのデメリット5選

① 異動・転勤リスクで生活が圧迫される
教員は異動や転勤がある職種です。
ブロック型・広域型の県では、通勤距離が大きく変わることも珍しくありません。
「夫が西部、妻が東部の学校」などになった場合、交通費や時間の負担が家計を直撃します。
せっかくマイホームを手に入れても、“ほとんど家にいない”という本末転倒なケースも。
② 片方の休職・育休・病休・離職で返済負担が急増
ペアローンは「2人の収入が前提」で成り立つ仕組みです。
しかし、産休・育休・病休・介護など、どちらかが一時的に収入減となることは教員家庭でもよくあります。
また、私の妻は教員を辞めて個人事業を開業しました。教員を辞めるという決断には金銭的リスクが生じます。ペアローンには「教師を辞める」という選択肢を狭める恐れがあります。
返済計画を立てるときには、「どちらか1人でも返せる額か」を必ず確認することが大切です。

③ 諸経費が“2本分”かかる
ペアローンは契約が2本になるため、事務手数料・保証料・司法書士費用などの諸経費も倍増します。
また、将来的に繰上返済や借換えをする際も、手数料がそれぞれに発生します。
見落とされがちですが、長期的には数十万円単位の差になります。
④ 万が一のときも“半分だけゼロ”
団体信用生命保険(団信)により、契約者に万が一ことがあった際はローン残高が0になる仕組みがあります。
しかし、ペアローンの場合は亡くなった方の分のみが対象。
もう一方のローンはそのまま残ります。
残された配偶者が1人で支払いを続けられるかどうか、慎重にシミュレーションしておく必要があります。
⑤ 離婚・別居時の処理が複雑
ペアローンの大きなリスクのひとつが離婚時の対応です。
マイホームの名義は共有、ローンも2本。
売却には両者の同意が必要で、どちらかが反対すると処理が進みません。
さらに、売却額が残債を下回る場合は離婚後も返済義務が残ることもあります。
現実的には、ペアローンを組んだまま別居・離婚をするとトラブルが多発し、大きなストレス要因になります。
もちろん、住宅購入の際に離婚を想定することは、感情的には難しいと思います。
しかし、そこは感情とは別に数字で冷静に判断する目線も重要です。
ペアローンを検討するなら“ここをチェック”
| 項目 | チェックポイント |
|---|---|
| 返済比率 | 夫婦それぞれの手取りの20〜25%以内 |
| 異動・転勤 | 片方が通勤1時間超にならないか/勤務ブロックの変動に耐えられるか |
| 育休・病休 | どちらかが無収入でも返済を継続できる金額か(生活防衛資金の有無も確認) |
| 維持費 | 固定資産税+修繕費(マンションは管理費・修繕積立金・駐車場代)を“第二のローン”として見積もる |
| 売却リスク | 万一の際に「貸せる/売れる」立地か(駅近・中古流通性・相場下落耐性) |
ペアローンを上手に活用するには
ペアローンを完全に否定する必要はありません。
共働きの強みを活かしつつ、リスクをコントロールできれば有効な手段です。
✅ 返済比率を控えめにする
✅ 固定費削減や積立投資を続ける
✅ 万一に備えた保険・生活防衛資金を確保する
✅ 物件は「資産価値が落ちにくい中古・駅近・流通性重視」で選ぶ
これらを守れば、“住宅ローンが家計の重しになる”ことを避けられます。

まとめ
- 教員夫婦は収入が安定しているため、ペアローンが通りやすい反面「借りすぎリスク」が高い
- 異動・育休・離婚といった変化に弱い仕組みである
- 契約は慎重に。「2人なら買えるから」ではなく、「1人でも返せるか」で判断を
住宅ローンは人生最大の固定費です。
家を“夢”で終わらせず、“戦略”として選ぶ視点を持つことが、先生方の家計を守る第一歩です。
固定費を見直して投資資金を生み出そうシリーズ
「教員のための「貯める力」入門 ― 生活満足度を落とさず、毎月5万円をひねり出す方法」
「固定費見直しシリーズ① ― 通信費を見直せば、月5,000円はすぐ浮く」
「固定費見直しシリーズ②― 保険の整理だけで月1〜2万円が浮く」
「固定費見直しシリーズ③ ― サブスクを整理して“自動出費”を止めよう」
「固定費見直しシリーズ④ ― 住居費を整えると家計は一気に軽くなる」
「教員は持ち家がいい?——住宅ローンの“借りやすさ”が生むメリットと落とし穴」
「教員夫婦でペアローンを組む前に知っておきたい5つの落とし穴」
「固定費見直しシリーズ⑤― 車のコストを整えると数百万円の差になる」
「車の残価設定ローンは本当にお得? 教員家庭が避けるべき“資産を減らす仕組み”」


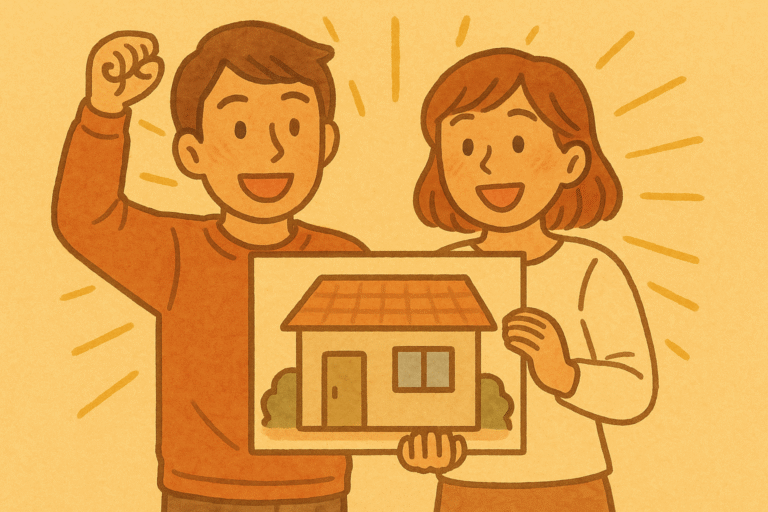


コメント