【40代教員の退職カウントダウン61:退職まで残り3年5ヶ月】
はじめに
「今日の休憩時間はスタバでコーヒー飲んでまったりしたよ」
もちろんこれは教員のセリフではありません。妻が教員から転職をして、驚いたことの一つに休憩時間がしっかり保証されているという事実でした。
教員時代では考えもしなかった「休憩時間にゆっくり休める」ことに驚き、そしてそれを楽しみにしていました。
一方学校の先生の休憩時間はというと、昼は給食指導や児童生徒の見守りに追われ、その後も心身を休める余裕はほとんどありません。
調査でも、小学校教員の平均休憩時間は10分未満。労働基準法で保障されている45分以上とは大きな差があります。
この記事では「教員も休憩は権利である」という点を改めて確認し、他業種との比較も交えながら休憩の大切さを考えたいと思います。
私は40代小学校教務主任(担任兼務)、2028年度末に正規教員を退職する予定です。
詳しくはこの記事をどうぞ→【私が退職しようと決意した具体的経緯】
法律で保障されている休憩とは?
労働基準法34条では以下のように定められています。
- 労働時間が6時間を超える場合 → 45分以上の休憩を与えなければならない
- 8時間を超える場合 → 60分以上の休憩を与えなければならない
ここで言う休憩は「労働から離れることを保障される時間」のことです。さらに「労働時間の途中に与える」「自由に利用できる」ことが原則です。休憩時間中であればコンビニに行こうがスタバに行こうが自由です。
つまり、給食を指導しながら食べる時間は休憩ではなく業務であり、放課中に子どもの見守りをするのも業務です。
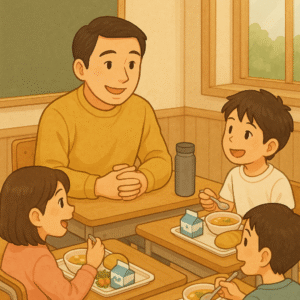
公立学校教員も地方公務員法58条を通じて労基法が準用されるため、当然この休憩規定が適用されます。
私の学校では、さすがに給食中を法的な休憩とすることはなく、昼放課中の15分と児童下校後の30分を休憩時間に振り替えています。
先生方はご自分の職場の法律で定められた休憩時間が何時から何時までかご存じでしょうか?
そしてその時間に休憩を取っていますか?
教員の実態:平均休憩10分以下
文部科学省や組合の調査を見ても、教員の休憩が確保されていない現実は明らかです。
- 文科省調査(2016年):小学校教員の休憩は平均9分
- JTU調査(2024年):37.5%が「休憩ゼロ」
- 全教調査(2022年):小学校教員の平均休憩はわずか4.1分
私の職場でも昼放課に委員会や生徒会を集めて指導するのは当たり前、子ども同士のトラブル対応や授業準備など、まともに休憩を取っている先生を見たことがありません。
一方で、一般企業の労働者は「45分〜1時間の昼休み+小休憩」が当たり前です。
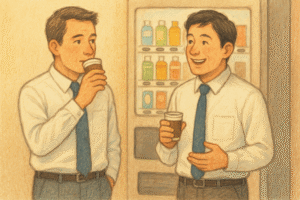
他業種との比較:教育の休憩は異常に短い
パーソル総合研究所の「休憩に関する調査(2024)」によると、一般労働者の休憩状況は以下の通りです。
- 昼休みに 46〜60分休憩する人が56.3%
- 61分以上休む人も22.4%
- 30分未満はわずか3.1%
法的に言えば休憩時間は自由に過ごすことが保証されています。つまり、コンビニにいったり、自販機でコーヒーを買いに行ったり、仮眠を取ったりするのも自由です。
さらに、半数以上が昼休み以外にもコーヒーや雑談などの小休憩をとっています。
一方「教育・学習支援業」では45分未満の休憩しか取れない人が37.8%と全業種で最悪レベルでした。医療や金融よりも短い上に、学校外で休憩をとるという人はほとんどいません。
運輸業界では過労死防止のため「連続運転は4時間以内・30分休憩義務」「勤務間インターバル11時間」など厳格な基準があるのに比べると、教員の休憩は国際基準からも大きく遅れています。
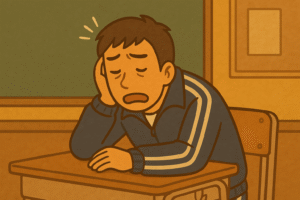
合わせて読みたい:先生の労働条件シリーズ
「教員不足は2030年代に解消?データから未来を考えてみた」
「教員給与の現状・将来見通しと他業種との比較(2025年時点)」
「公立小中学校の非常勤講師:勤務形態・待遇の実態と現実的な選択肢としての可能性」
「40代教員の退職後プラン|常勤講師の給与比較から見える現実」
「第2の人生の軍資金?自己都合退職の場合、退職金はいくらもらえるの?」
休憩をとるメリット
休憩をとると以下のような効果があります。
- 気持ちがリセットされる:イライラが和らぎ、子どもに優しく接する余裕が生まれる
- 午後の疲労感を軽減:10分の仮眠でも午後の授業に集中できる
- ミス防止:採点や児童対応の判断力が落ちにくい
休憩を阻む「意識の壁」
なぜ法律で定められているのに休めないのか
- 子どもの安全を守らなければならない責任感
- 教員不足・校務多忙による物理的な忙しさ
- 「休むのは悪いこと」という風土
- そもそも休憩時間が法的に認められているという認識がない
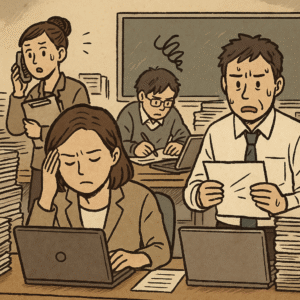
さらに、現場では「業務の間に休んだところで結局残業が増えるだけ」という現実感があります。
業務量が変わらない以上、「今のうちに片付けよう」と休憩を削ってしまうのです。
まとめ:堂々と休もうと言いたいが、、、
制度や文化を変えるには時間がかかります。私たち自身が「休憩は権利」と認識し、後ろめたさなく休むことが大切です。休憩はサボりではなく、教育の質を高めるための準備時間です。午後に笑顔で子どもと向き合えるよう、堂々と休みましょう。
と、まとめたいのですが業務量の実情や子ども同士のトラブル対応を考えると現実的ではありませんね、、、
まずは知ってください!
我々は労働者のなので労働基準法で「休憩する権利」が認められているということを。
その休憩というのは、業務から解放されることが保証された時間で、自由に利用することができる時間であるということを。
その意識改革が、きっと労働環境の改善を前に進めてくれるはずです!
合わせて読んで欲しい:教員の健康を考えるシリーズ
【教員の健康を考えるシリーズまとめ|休憩・食・睡眠・姿勢・ストレスケアで整える働き方】


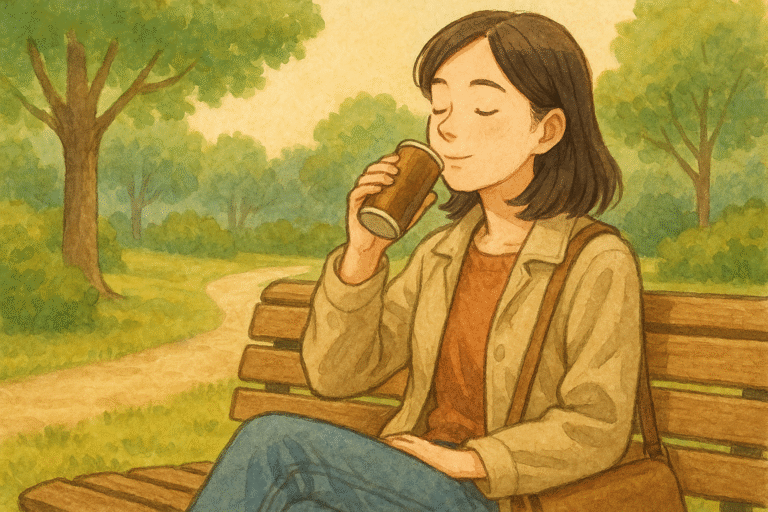
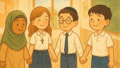
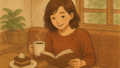
コメント