【40代教員の退職カウントダウン60:退職まで残り3年5ヶ月】
はじめに
「外国籍児童を受け入れるときに最も難しいのは宗教対応だ」
担任をしていて、そう感じた先生は少なくないはずです。
以前の記事で共有したように、今日本の教育現場にどんどん外国籍児童が増えてきており、10年前と比べると倍増、外国籍児童生徒を受け入れている公立学校は1万3000校にのぼります。
もはや外国籍児童の対応はどの先生も他人事ではありません。
「学校現場で増える外国籍児童への対応|宗教・文化・生活習慣を踏まえた支援とは」
「日本に増える外国籍児童生徒と学校現場の対応 ~もう一つの特別支援教育~」
文化の違いから生じる摩擦の多くは、実は宗教に起因しています。
私は40代小学校教務主任(担任兼務)、2028年度末に正規教員を退職予定です。
詳しくはこの記事をどうぞ→【私が退職しようと決意した具体的経緯】
私の専門は社会科です。そこで今回は、世界人口の大半を占め、学校現場でも摩擦が起きやすい一神教(ユダヤ教・キリスト教・イスラム教)について、学級経営の視点から先生方に情報を共有したいと思います。
宗教理解が必要な理由
- 食事や行事など「学校生活のルール」と「宗教上の決まり」がぶつかることがある
- 子どもにとって宗教は「家庭とアイデンティティの核」であり、尊重されないと孤立や不信感につながる
- 宗教知識がある先生は、外国籍の保護者との信頼関係を築きやすい
例えば、給食で食べられない食材、ラマダーン中の断食、男女の関わり方や服装の違い…。
日本人は「自分は無宗教」と考える人が多いため、宗教を重要視する感覚を持ちにくいのですが、世界の多くの国では宗教が日常生活の基盤になっています。
だからこそ、先生が宗教の基本を知っておくことは、外国籍児童生徒の理解に直結します。
つまり、宗教理解は「異文化対応スキル」であり、これからの時代、クラス運営の基盤になる力です。
一神教とは?
多くの宗教は「神様の存在」を中心に据えます。その中で、一神教は「唯一の神のみを信じる」宗教で、代表的なものがユダヤ教・キリスト教・イスラム教です。
ちなみに日本神道は「アマテラス大神」や「スサノオの尊」、さらには「野球の神様」や「トイレの女神様」まで神様がたくさん存在する多神教です。日本に馴染みのある仏教も多神教と言えるでしょう。
ユダヤ教やイスラム教は唯一絶対の一つの神様が存在するので一神教です。
以下にその特徴等を紹介しますが、信者の信仰にも濃淡があり、全てを厳格に守っているわけではありません。基本的な知識として捉えてください。
ユダヤ教
- 約4000年の歴史を持つ最古の一神教
- 旧約聖書を聖典とし、唯一神ヤハウェ(エホバ)を信じる
- 信者数は少ない(約1200万人)が、歴史的影響は非常に大きい
- 聖地はエルサレム。ここを巡って他宗教とも対立
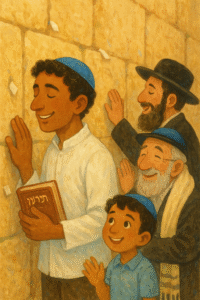
教師として知っておきたいこと
- 食事(コーシャ)
- 豚肉・貝類・血の混じった肉などは禁止。
- 乳製品と肉を同じ食事で取らないなど細かな規則あり。
- 日本の給食対応は難しい場合が多く、弁当持参のケースが多い。
- 安息日(シャバット)
- 金曜の日没から土曜の日没までが「安息日」。
- この時間は労働や勉強を避ける家庭もあり、学校行事と重なると参加できない場合がある。
- 金曜の日没から土曜の日没までが「安息日」。
- 服装・儀式
- 男子は「キッパ」と呼ばれる小さな帽子を着用することがある。
- 宗教的儀式や祈りを大切にしており、エルサレムなど聖地との結びつきが強い。
- 男子は「キッパ」と呼ばれる小さな帽子を着用することがある。
キリスト教
- 紀元1世紀、イエス・キリストの教えから始まった
- 新約聖書を聖典とし、救世主(メシア)イエスを通して神とつながる
- 4世紀にローマ帝国の国教となり、ヨーロッパを中心に世界へ拡大
- 現在は世界最大の宗教
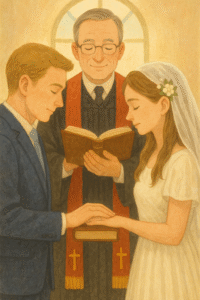
教師として知っておきたいこと
- 食事
- 基本的に食制限は少ないが、一部宗派では金曜日に肉を避ける、断食期(四旬節)に特定の制限がある。
- 基本的に食制限は少ないが、一部宗派では金曜日に肉を避ける、断食期(四旬節)に特定の制限がある。
- 行事・儀式
- 教会行事や日曜日の礼拝を重視する家庭もある。部活動や学校行事と重なる場合に配慮が必要。
- 宗派によって「偶像(像や神社的要素)」を避ける立場があり、特定の儀式に違和感を持つ保護者もいる。
- 教会行事や日曜日の礼拝を重視する家庭もある。部活動や学校行事と重なる場合に配慮が必要。
- 文化的特徴
- クリスマスやイースターなど宗教的行事を重視。
- 日本の学校行事に宗教的色彩がある場合(例:初詣的活動)に慎重になるケースがある。
- クリスマスやイースターなど宗教的行事を重視。
イスラム教
- 7世紀、アラビア半島でムハンマドによって広まった
- コーランを聖典とし、神アッラーの言葉そのものとされる
- 豚肉や酒を禁じる教え、断食(ラマダーン)、礼拝など日常生活と直結
- 世界で急速に信者が増加している宗教
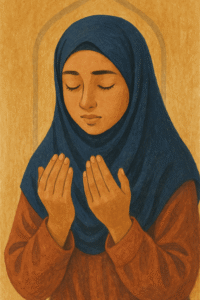
教師として知っておきたいこと
- 食事・給食
- 豚肉・アルコールは禁止(加工食品にも注意)。
- ハラール食を求める家庭もあり、弁当持参や代替食で対応することが多い。
- ラマダン時期は日中断食 → 給食を食べない、体調への配慮が必要。
- 豚肉・アルコールは禁止(加工食品にも注意)。
- 服装・体育
- ヒジャブ(スカーフ)を着用する女子生徒もいる。
- 体育・水泳では肌の露出を避けるため、長袖・長ズボンや専用の水着を使用。
- 男女一緒の水泳授業に抵抗がある場合もある。
- ヒジャブ(スカーフ)を着用する女子生徒もいる。
- 礼拝
- 1日5回の礼拝が基本。学校生活で時間・場所を求められる場合がある。
- 教室や会議室を祈りの場にする事例も。
- 1日5回の礼拝が基本。学校生活で時間・場所を求められる場合がある。
学校現場で起こりやすい摩擦と宗教的背景
- 給食:宗教上の決まりで食べてはいけない食材がある。宗教儀式としての断食がある。
- 体育・水泳:宗教上の決まりで肌の露出を避けなければならず、男女で一緒に活動することに抵抗がある。
- 行事:神社の鳥居をくぐってはいけない、合唱等で歌ってはいけない種類の歌がある、「〇〇の神様」や「バチが当たる」という表現を受け入れてはいけない、祈りの時間を確保したい
- 保護者対応:宗教的価値観から日本の学校文化に違和感を持つ

背景を「文化」とだけ捉えるのではなく、「宗教に根差した理由」と理解することで、保護者や子どもの抵抗感が理解しやすくなります。
日本人が忘れがちな宗教の存在感
- 日本では「無宗教」と答える人が多いが、実際は初詣やお墓参り、祭りなどに自然と参加している
- つまり「宗教を意識しない文化」に慣れているだけで、他国から見ると十分に宗教的な営みをしている
- その感覚の違いが、外国籍児童や保護者との摩擦を大きくする

先生に必要な宗教リテラシーとは?
- 世界宗教の基礎を押さえる(特に一神教の共通点と違い)
- 学校生活で摩擦が生じやすいポイントを理解する(食事・礼拝・服装・行事)
- 保護者の宗教観を尊重する姿勢を持つ
- 児童にも異文化理解教育を行い、偏見や誤解を防ぐ
まとめ
外国籍児童を受け入れるときに、宗教は最大の摩擦要因になり得ます。
だからこそ、先生こそ宗教の基礎を知り、違いを理解する姿勢を持つ必要があります。
ユダヤ教・キリスト教・イスラム教は「唯一の神を信じる」という共通点を持ちながら、仲介者や聖典の違いで発展し、今もなお複雑な関係を続けています。
その知識を持つことで、給食・行事・服装・保護者対応など、学校現場の具体的な配慮につなげることができます。
- 事前確認が必須:同じ宗教でも家庭や宗派で解釈が異なる。必ず本人・保護者に確認すること。
- 学校文化との違いを説明:掃除・給食・水泳など「日本では当たり前」が摩擦になりやすい。
- 代替案を用意する:行事・給食・体育などでは「代替参加」「弁当持参」「見学」など柔軟に。
- 多文化共生の学びに活かす:クラス全体に背景を説明し、相互理解の機会にする。
👉 異文化理解の第一歩は「宗教理解」から。
先生自身が学び、クラス全体で共有することが、摩擦を「学び」に変える力になります。


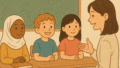

コメント